第一章 働くという事と福祉の現状
訪問介護の現場では、慢性的な人手不足と厳しい報酬体系の中で、ヘルパーたちが日々限界まで動いています。
訪問介護の多くは「家庭の事情で長時間で働けない人」が担っています。
子育て中、親の介護を抱えながら、時間をやりくりして、わずかな収入とやりがいで働いています。
私は、その現場を運営する立場にいます。
色々な制度の設計と現実との乖離を見ていきましょう。
第二章 家庭と仕事の両立
私の事業所には、子どもの通学時間にあわせて午前中だけ働くシングルマザーのヘルパーがいます。
また、親の介護があるためにフルタイムの仕事に就けず、訪問介護の1日1.2件の仕事に希望を託す方もいます。
1勤務が終わるごとに自宅に帰りたいヘルパーが一定数います。私も家庭の事情上、そうでした。
こうした方々に共通するのは、「生活のために働きたいけど、捻出する時間も体力も限られている」という現実です。
訪問介護の現場では、ヘルパー1人が複数の利用者宅を回り、短時間のサービスを積み重ねて日々を成り立たせています。
◯訪問介護の報酬として(事業者側として)
【そもそもの単価】
【何が理不尽か】
- 大規模事業所による、訪問介護の施設的運営がある。
- 訪問介護の施設的運営は利益率が高い(従来の訪問事業よりは)。
- それに基づいて報酬削減が決まった。
従来の訪問介護事業は移動費が出ない。
「特に過酷な状況にある」と指摘しています。
【処遇改善加算】
処遇改善加算とは、介護職員の給与を補助するため、一定の条件を満たす事業所に支給される制度です。
制度上、「処遇改善加算」や「ベースアップ加算」などの仕組みによって、収入の底上げは図られており、実際にヘルパー個人の給与にも反映されています。
ただし加算は、事業者側が毎年申請しないともらえません。
介護職の待遇を改善させようとすればするほど、
処遇改善加算に関する事務作業や環境整備にかかる時間や費用、
加算額以上の職員への支給等、これらすべてを事情者が負担しています。
【加算の具体的な内容】
- 例えば、処遇改善加算はどういう事をしている事業所なら加算I、加算Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ…と事業所により加算のランクがあります。それぞれの加算は行っている事業(届出内容)によって、決まっています(単価に対して何%入ってくるかが決まっています)。
- 処遇改善加算ⅠやⅡといった加算要件を満たすには申請時に、どんな良い事をしている事業所であるかといった、様々な職場要件を確認されます。
- そして、一般にはあまり知られていませんが、処遇改善加算は加算を算定するにあたり、加算額を全額、介護職員の処遇改善に使うことが義務付けられています。
- また、事業者は、毎年どのように職員に処遇改善加算を支給するかという計画を行政に提出し、翌年その計画通りに実行できたかという実績の報告もしています。
そもそも根本的な課題は「報酬が上がっても、それが実質的な“手取り”として残りにくい社会的構造」にあります。
◯ヘルパー(労働者側として)
訪問介護の多くは「家庭の事情で長時間で働けない人」が担っていますが、必ずしもそうとは言えません。
訪問介護のヘルパー側には、大きく分けて2種類のタイプの職員がいます。
- 家庭の事情等で、1勤務毎に自宅に帰りたいヘルパー
- 訪問介護という仕事が好きなヘルパー
- その他
1.のヘルパーは各事情に合わせて仕事の調整をしています。
訪問介護のように、誰にも気を遣わず、毎日数時間でも自宅へ帰れる可能性がある仕事。
この様な仕事はあまり無いように思います。
2.のヘルパーの問題点は、介護というより社会の構造の問題。
処遇改善等で額面の給与は上がっているが、
一般の職種と同じように「130万円の扶養控除」や「社会保険の壁」など、
働き方を制約する制度的な壁に当たっています。
人材不足と言われる介護業界ですが、この仕事が天職だという方もいます。
しかし、そんな中、2.のように、介護業界そのものよりも日本社会の構造が「もっと働きたい」という人に対して、それを制度が阻んでいる現実があるのです。
誰かの暮らしを守るために、なぜ自分の暮らしはこんなにも不安定なのか――
どうしてこんなに手取りが低くなるのか――
そう感じながら働く人は少なくありません。
次回
【現場の声】「家庭で支える前提」の訪問介護制度が、担い手を限界に追い込んでいる【中編】
・第三章 福祉事業者と福祉職員からみた制度の問題点
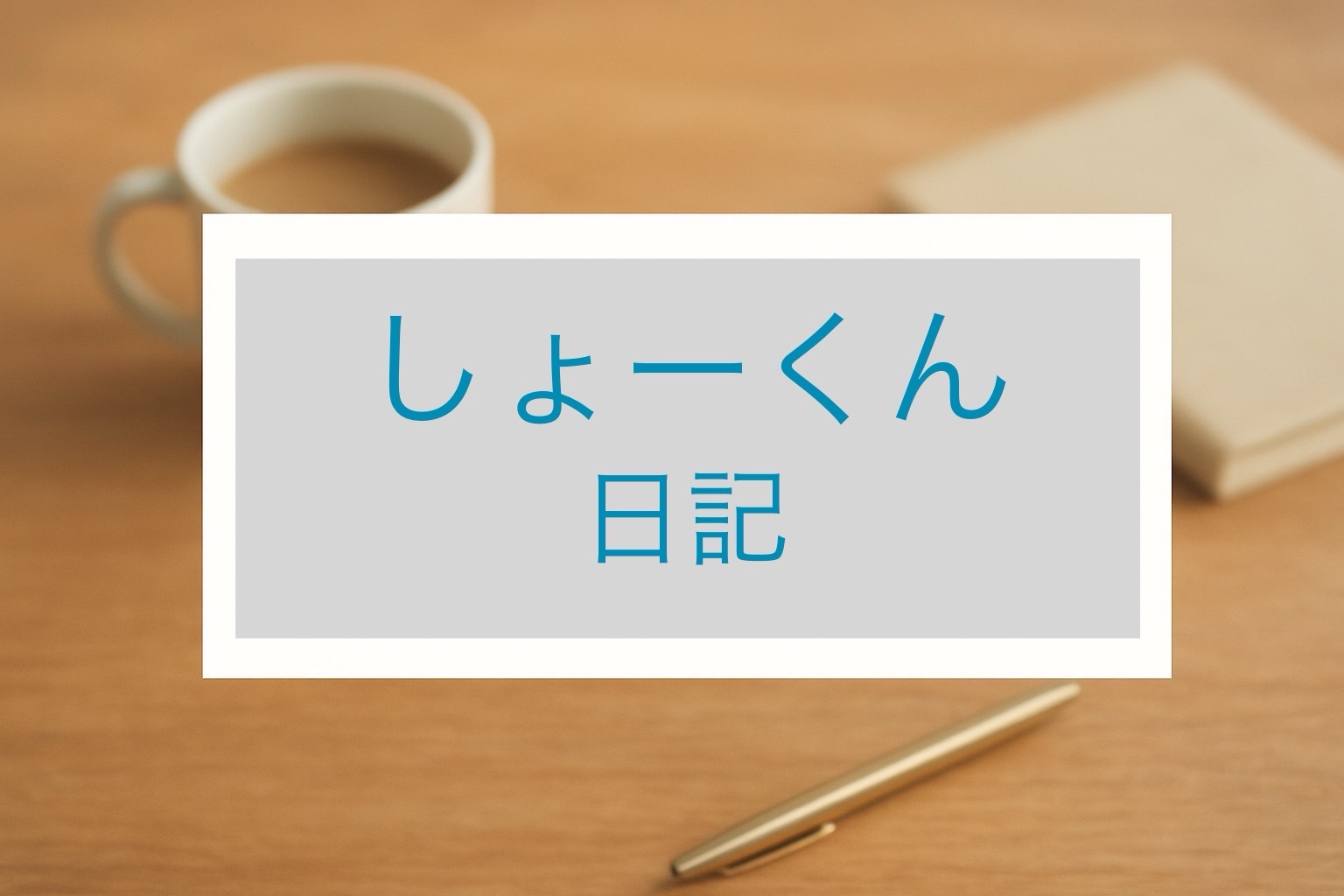

コメント