第三章 福祉事業者と福祉職員からみた制度の問題点
我が国では、介護は家族が行なってきたという歴史から、現在女性の社会進出、結婚後の共働き等昔と生活を取り巻く環境が大きく変わったにもかかわらず、制度全体が「家族がある程度支えること」を前提としたままである。
家族介護をなしに、訪問介護だけでは生活全体を支えるには限界があります。
中途半端に設計された結果「支援が入っているのに暮らしていけない」という矛盾した状況が生じています。
訪問介護の種類
近年、自宅ではなく、老人は全員施設に入ればいいじゃないか。
…という声もSNSなどで聞きます。
これに近い現象が起きています。
施設的訪問型(効率運営が可能なケース)
- 同一建物での対応
- 移動時間・調整が最小限
- より低単価でも運営が成り立つ
在宅型訪問介護(個別支援型)
- 1人ひとりの家を回る
- 移動時間・調整労力が大きい
- 報酬水準を上げないと成り立たない
近年では、効率的な運営によって収益を確保する「施設的訪問介護」が増加しています。
運営の仕方は違いますが、単価は同じ。実態が乖離してきています。
詳しくは、前記事の『何が理不尽か』をご覧ください。
しかし、これはサービス提供側の工夫の成果であり、すべてを否定するべきものではありません。
なぜ従来型の訪問介護が必要なのか
一方で、世間で推奨されている施設に一旦は行っても、
退所する・させられる人が、一定数います。
なぜか。
出てきた人達に話を聞くと…
好きに買い物もできない。外食もできない。
ごはんがまずい。偏食の自分には耐えられなかった。
ジャンクフードもお菓子もアイスもジュースもない。
パットを3枚に重ねられて寝苦しい。足もしんどい。
おむつが濡れていないのに、職員が夜中に変えに来る。
家でいた時よりも、おむつ代がすごくかかる。
施設の職員に子ども扱いされた。話し相手がいない。
話しかけても返事が返ってこない。
友達・知人に気軽に会えない。職員に自分が怒られたんじゃないけど怖かった。
嫌いな利用者・職員がいた。
家でいると当たり前のことを希望したら、施設を追い出された。
ペットと暮らしたい。
時間に縛られてシンドイ…等
現役世代に言いたいのは、老後ではなく、
今のあなたは、この状態に耐えられるかどうかです。
ただし、上記の問題点のいくつかは改善できるはずなので、いったんここでは先に進みます。
私が言いたい根本的な問題は、現状が改善されようとされまいと…
『施設入所は、誰かに管理される環境下で暮らす』という点。
施設側にも責任があるので、管理を緩和していくのは難しいでしょう。
現状、ちょうどいい暮らしが存在しません。
現状に限って言うのであれば、一番いいのは入所し、時々家に帰れることかもしれません。
しかし、前提条件として、家族が受け入れてくれる場合に限り、時々帰れる可能性がある。
家族の理解がない人や家族の負担が大きい人、家族がいない人は、帰りようがない。
結果、我慢できない場合は、自ら退所する事になります。
そうなると、将来どう転ぶにしても、訪問介護がないと日常生活を維持することは厳しい。
施設利用者側が、自宅に帰ってくる理由は、
介護で言われる自己決定・自己選択により自立していたいからです。
訪問介護は、あくまでピンポイントでの介入になるので、
本人のQOL(生活の質)も高く保ちやすい。
訪問介護のメリットはこれだけではありません。
訪問介護が減ると、困るのは「低所得者層」
現実には、そもそも入所できない人もいること。
- 生活保護受給者を除く低所得の高齢者が
- 特養には入れず、有料老人ホームの自己負担は高く
- 結果的に訪問介護が「唯一の選択肢」
このような世帯が数多くあります。
それにもかかわらず、訪問介護の報酬を下げることは、
「最後のセーフティネットを縮小すること」に他なりません。
これは、弱者の孤立化を招き、最終的にもっと大きな社会コスト(入院、介護難民、孤独死、虐待)を生むリスクを孕んでいます。
なのに、制度上は「削減対象」「軽視対象」として扱われる。
これは完全に矛盾です。
訪問介護の崩壊はもう目の前に迫ってきています。
私たちはこのまま崩壊を見過ごすしかないのか?
介護の未来はどうなるのか?
次回
【現場の声】「家庭で支える前提」の訪問介護制度が、担い手を限界に追い込んでいる【後編】
・第四章 制度改善のための具体的な提案
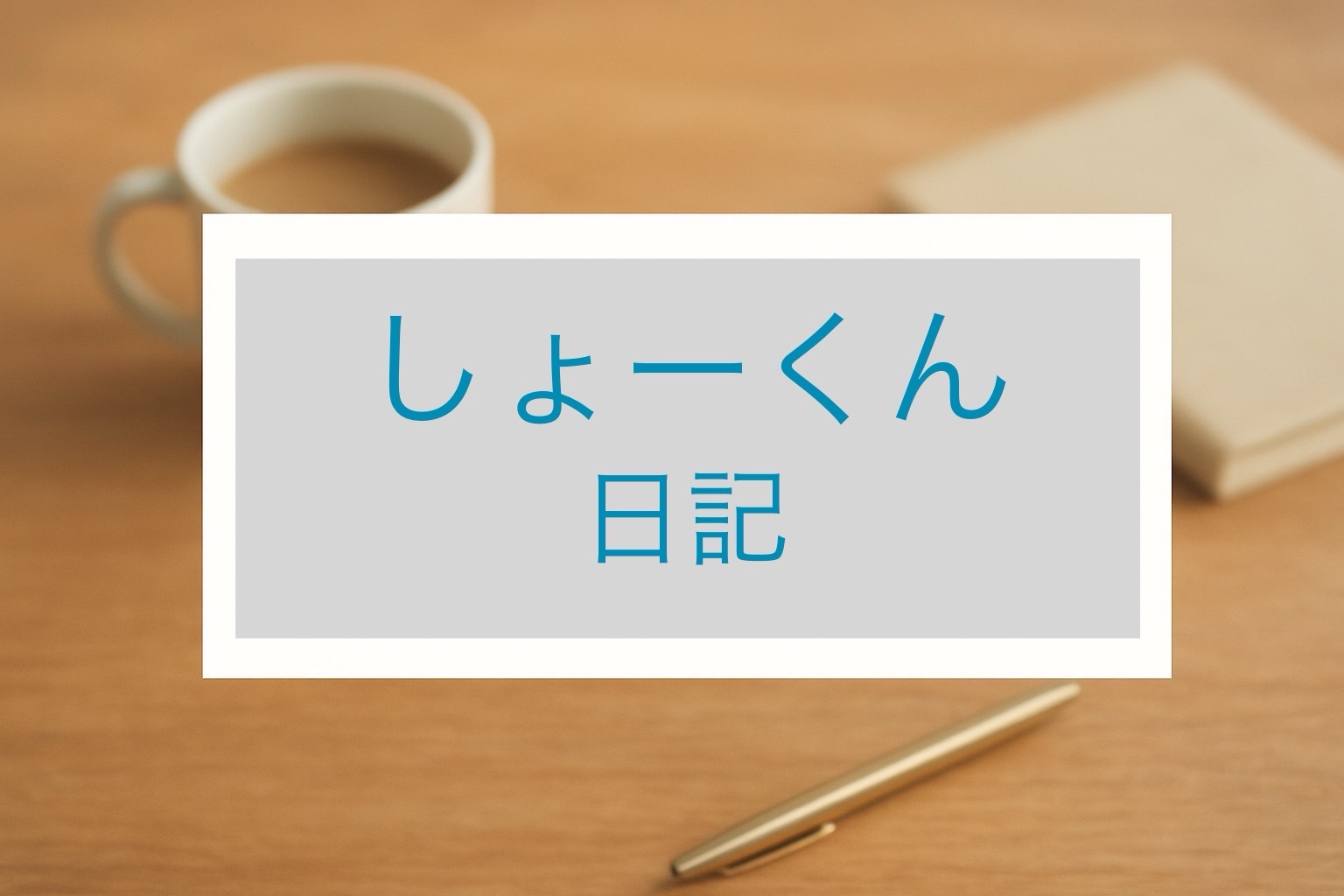

コメント