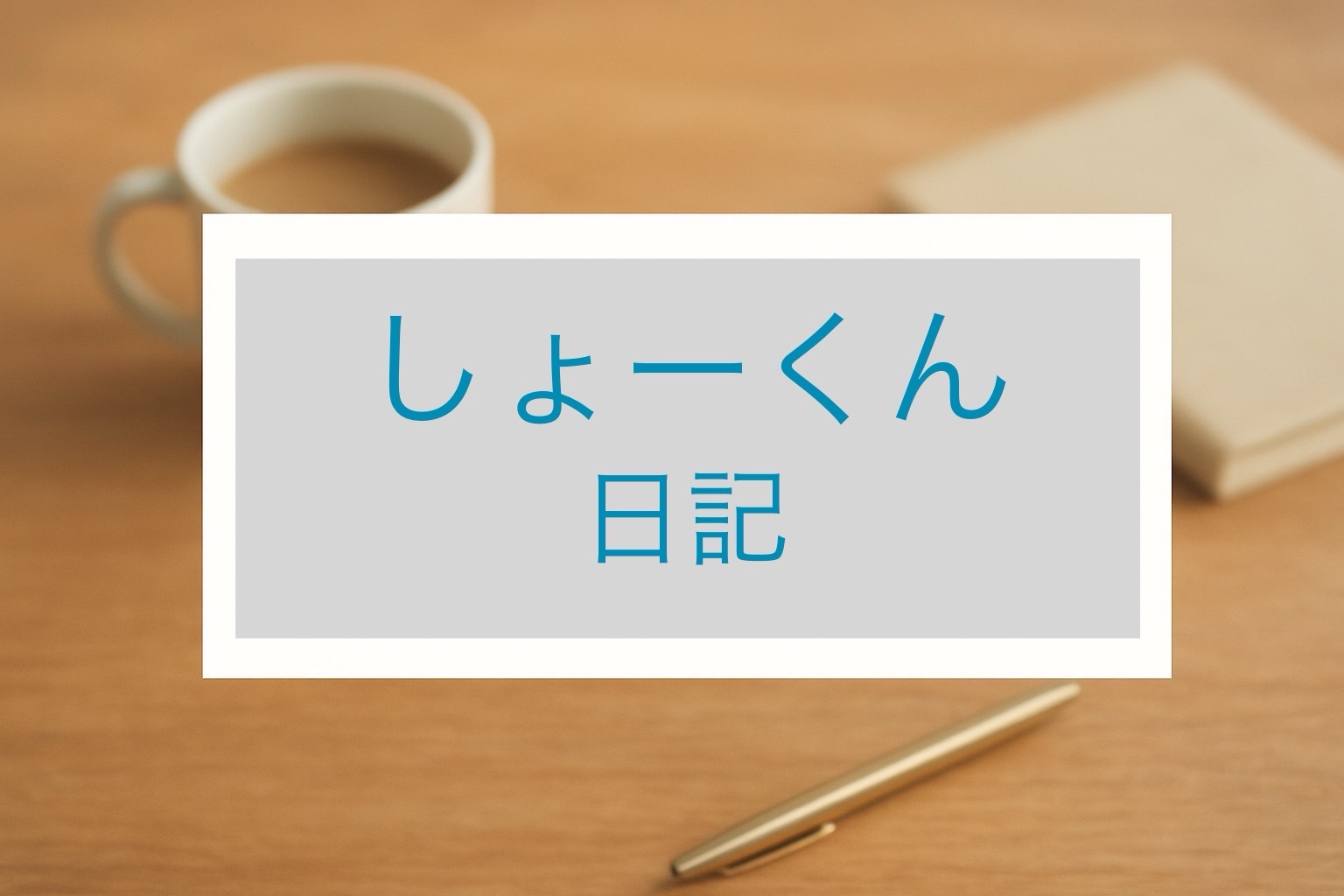― 人材確保・職場環境改善等事業補助金にも活用できる実践資料 ―
▶後編ではQ&Aで検討しています。興味がある方はこちらからどうぞ。
作成日:2025年5月
【この資料の活用例】
・現場会議で付箋やホワイトボードと組み合わせて使う
・人材確保・職場環境改善等事業補助金の申請書作成に添付する
・新人研修や内部研修で「課題把握〜解決までの流れ」を説明する教材に
【注意事項】
・本資料は参考用であり、必ずしも行政の判断を保証するものではありません。
・現場に合わせてカスタマイズしてご利用ください。
業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の見える化の実施を計画/実施
【課題の把握】『業務中の気づき等(なんでもOK)』『付箋等で全体を眺めよう』
『お題:どんなことに苦労しているとか悩みとか何かあるか?』
とりあえず職員にきいてみた。
Aさん:書類で報告するのか。電話で報告するのか。報告する内容か、迷いは多い。
Bさん:計画以外の利用者さんの癖・好みが把握できれば助かる。どこのメーカーの飲み物・食べ物なのか、変更はないのか買い物の聞き取りに神経を使う。
Cさん:掃除もある程度でパターンが変わったりする。久しぶりに入った利用者さん宅は行ったことがあってもやはり難しく感じる。
Dさん:洗濯の干し方も利用者さんごとに干し方が違い、覚えていないと注意を受ける。よく行くお宅は覚えるがやはり細かいことが負担になる人はいると思う。
【課題の分析】『話し合い』
付箋に書き出し、みんなで話し合う。
『事務所にどこまで聞いていいか迷う』『先輩にどこまできけばいいか聞いていいか迷う』『報告方法に悩む』『各ご家庭のやり方がある』『覚える負担』『どこのメーカーが好きか』『どの手順なら利用者から怒られないか』『たまに入ると気づかないうちに、利用者のこだわりを忘れてたりがある』『初めての家はいっぱいいっぱいな気持ちで仕事をする』
『原因』
① 報告など自己判断についての悩みを相談したい/悩みたくない。
② 実際サービスを提供する時は、職員と利用者双方が気持ちよく関わりたい。円滑に乗務を遂行する為には、各利用者の細かい特徴を捉える必要があるが、情報が完全には共有され切ってはいない。
『解決すべき課題を決める』
① 報告や利用者さんについての悩みについての解決方法が必要
② そもそも悩まなくていいようにすることが必要
③ もっと個人の好みなどの詳細な情報が欲しい
『影響』
① 利用者個人の好みや傾向を覚えていないと利用者の負担になる。
② また、業務遂行にあたり、個性を覚えないといけないことは、新規ヘルパーさんにとってはプレッシャーになりうる。
③ 元々居る職員としても、新人に教え切るのは難しい。業務内容や計画の方針、人となりは事務所からの事前情報や訪問の同行で伝えられても、生活するにあたっての好みまでとなると情報量が多すぎて教えるのも困難。
『解決方法』
※ちょっとした愚痴や相談等から質向上の為の課題や良い支援が見つかることがある。もっと堅苦しくない連絡方法をつくってみてはどうか。
=各、利用者ごとにグループLINE等を作り、当職員間での連携を図るのはどうか?
上記書類と、下記根拠書類を見せた時のChatGPTの回答
結論
2025年度に関しては、人材確保・職場環境改善等事業補助金や処遇改善加算については、「現場での課題洗い出しや計画立案の段階でも算定可能」と明記されている。
よって人材確保・職場環境改善等事業補助金や処遇改善加算については、LINEに限らず『何かしらの通信手段を検討した』としただけでも、今回は認められる。
そして、現場運用上は退職者の即時退出+参加者一覧確認により、実務的なリスクはほぼゼロ。
通信システムの導入を検討するのにLINEからはじめて見ることは、実務上良い方法ではあると判断できる。
※ICT導入補助金や雇用・労働業務改善助成金等は今回の運用には直接関係しない。
以下根拠書類に、下記を添付します。
①補助金申請の為の取り組み事例
👉職場環境等要件
②Q&A
③行政指導や監査のリスクについての検討
※私は今回①の1. 「現場の課題を見える化」を選択しました。
① 職場環境等要件
~生産性向上のための導入編~
以下の1.から3.のうち、いずれか1つの取組を実施すれば、介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金を受け取ることができ、処遇改善加算の職場環境等要件の適用も免除されます!
以下の取組は1つの例であって、各事業所の実情に応じて、様々な取組を実施しましょう!
1.「現場の課題を見える化」はこちら!←※私は今回これを選択。
【STEP1】課題を把握する
▶業務中の気付き等(何でもOK)
▶付箋等で全体を眺めよう
【STEP2】課題を分析する
▶課題は何か話し合おう
▶解決すべき課題を決めよう
※一度に全て解決しようとしなくてOK!
※2025年度に関しては、「解決するべき課題を決めよう」までで終わっている。
そして「※一度に全て解決しなくてよい」と明記されている。
これは、
=「現場での課題洗い出しや計画立案の段階でも算定可能」
という意味である。
2.「業務内容の明確化と役割分担」はこちら
【STEP1】業務と役割を整理
▶業務を洗い出そう(誰が・いつ・どこで・何を)
▶役割を決めよう(機能訓練/マネジメント/書類整理等)
【STEP2】業務分担表の作成・運用
▶「Aさんはこの時間はこの業務」と固定配置
▶役割分担表の作成
▶まずは試し、ブラッシュアップしていく
※できる範囲からでOK
3.「業務改善活動の体制構築」はこちら!
【STEP1】職員同士で集まる
▶2~3人からでもOK
▶新しいことに意欲的なメンバーに声がけを
【STEP2】テーマを決める
▶理念の浸透、手順書作成、5S活動等
▶5S活動(※)は効果を体感しやすいためオススメ
※整理・整頓・清掃・清潔・躾(しつけ)
【STEP3】活動の実施を所内に周知する
▶正式な業務に位置づけ、意義や進め方を共有
(説明会の実施だけではなく、所内報でもOK)