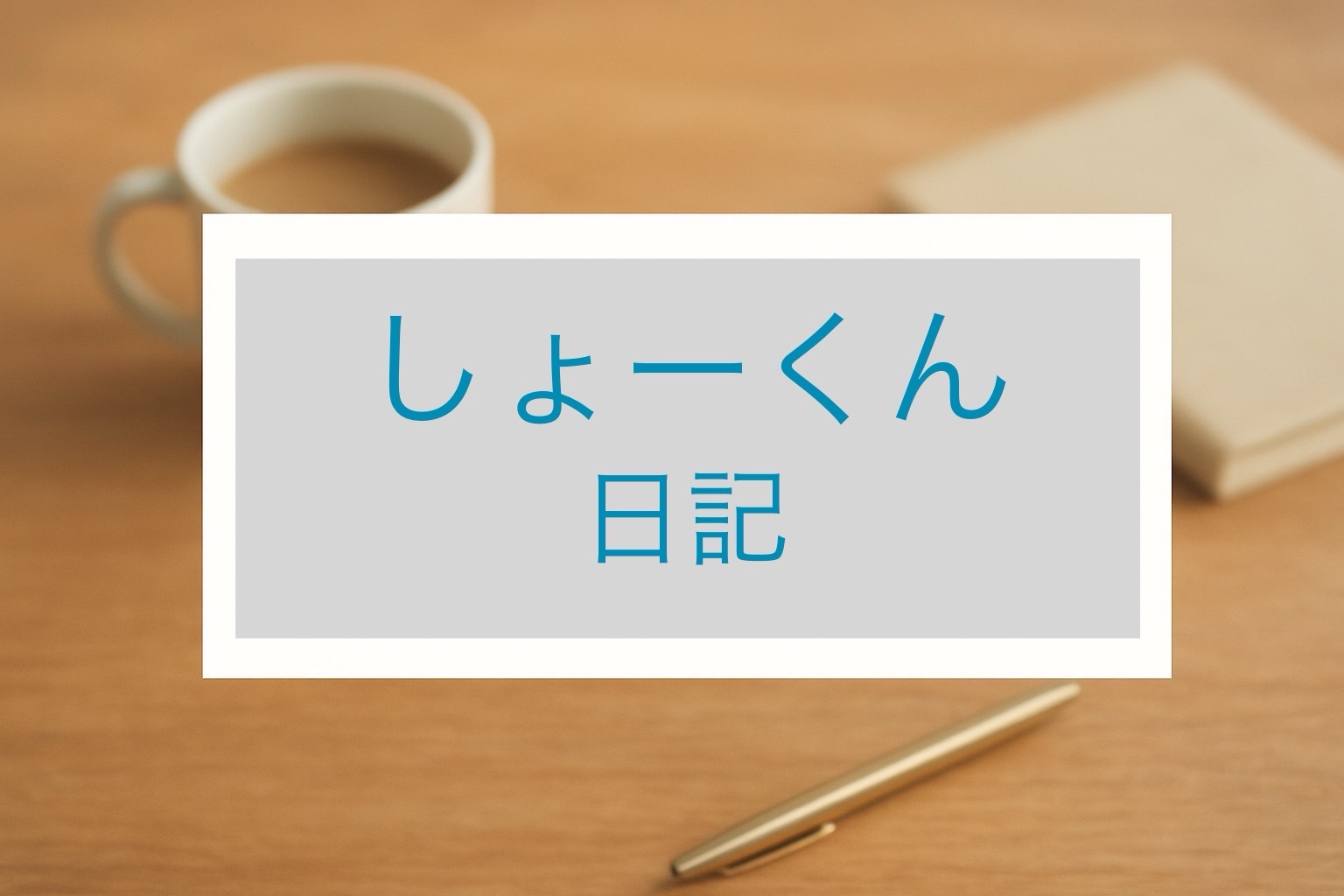― 人材確保・職場環境改善等事業補助金にも活用できる実践資料 ―
▶前編での課題の把握。実際のやり取りについては、こちらからどうぞ。
②Q&A形式
Q1.(あーちゃん): LINEで情報共有することにはどのようなリスクがありますか?他の方法でも同様に情報管理はされていると思うのですが。
A1.(ChatGPT): LINEは便利ですが、個人端末に情報が残る仕組みで、行政や補助金の観点では「管理責任の所在」が曖昧と見なされやすいです。現場で管理していても、形式上のリスクとして指摘される可能性があります。
Q2: システムによる情報管理の差はどの程度あるのでしょうか?機能面では大きな違いはないと思うのですが。
A2: 機能的には大きく違いません。ただ、法人用システムは「誰が送った・見た・退職者を除外した」がログで残り、行政に説明可能です。個人用LINEは、端末依存でログを集中管理できません。
Q3: 退職者をグループから削除すれば問題はないのではないでしょうか。
A3: 現場運用としてはそうです。退出通知や参加者一覧で管理すれば、情報漏洩リスクはほぼゼロです。ただし行政は「公式に管理されているか」を重視するので、形式的には個人端末依存と見なされます。
Q4: LINEのグループ管理では退出通知が出ますし、現在の参加者一覧も確認できます。管理記録が残らないとはどういう意味でしょうか。
A4: 現場ではその通りです。誰が入っていて誰が抜けたかは把握できます。しかし行政や補助金審査では、個人端末の履歴を証拠として提出するのは現実的ではないため、形式的なリスクとして扱われます。
Q5: スクリーンショットを撮ることは、LINEに限らずスマホ上で可能だと思います。スマホアプリの漫画などでも同様ではないでしょうか。
A5: 技術的には可能です。問題は「できるかどうか」ではなく、行政が「管理者として責任を果たせるか」をどう評価するかです。法人用システムならログが残り、説明責任を果たしやすくなります。
Q6: グループラインを使用するので、やり取りは個人端末に依存しているわけではありません。退職者は即座にグループから削除されますが、それでも問題となる可能性はありますか。
A6: 現場ではその通りです。LINEでの退職者管理は適切に運用すれば問題ありません。行政が言う「個人端末依存」とは、形式上の懸念に過ぎず、実務上の問題ではありません。
Q7: 無料で利用できるLINEで十分である中、なぜ月額アプリの導入を推奨するのでしょうか。コストや作業負担の面で現場の利便性に影響しないでしょうか。
A7: 月額アプリを勧める理由は、行政や補助金で「誰がいつ見た/送った/退職者を除外したか」の管理責任を明確に示せる点です。現場ではLINEで十分便利で、入力の二度手間やコストもかかるので、現場効率の観点では月額アプリは必須ではありません。
Q8: 補助金の形式的な安全性を求める場合にのみ月額アプリを使用するという理解で正しいでしょうか。その場合、どのようなリスクを回避できるのでしょうか。
A8: はい、その通りです。現場改善レベルならLINE運用で十分です。行政・補助金上は、形式的に安全性を示す必要がある場合だけ法人用システムを使う、という二段構えで考えられます。
Q9: 現場運用は本当に安全なのでしょうか。形式的リスクを指摘される場合でも、実際に問題が発生する可能性は低いのではないでしょうか。
A9: 現場・行政の両面から評価すると、ユーザーさんの運用方法(退職者の即時退出+参加者一覧確認)は、現場運用としても安全です。行政や補助金が懸念するのはあくまで形式上のリスクで、実際に大きな問題が起きる可能性は非常に低いです。
③行政指導や監査のリスクについての検討
【現場向け】LINE運用ガイド(監査・行政指導対応版)
1. 目的
・利用者情報や業務連絡をスムーズに共有
・現場での情報漏れや連絡漏れを防ぐ
・行政や補助金審査の形式的要件にも対応可能な運用を意識する
________________________________________
2. 運用ルール(基本)
①グループ作成
・利用者ごとに職員グループを作成
・利用者名や重要情報を簡潔に扱う
② 参加者管理
・退職者は即座にグループから削除。
これをすることで、退職者はやりとりが見れなくなる。
・参加者一覧を定期確認し、現状を把握
③ 情報の扱い
・個人間でのやり取りは、個人端末に情報が残る仕組みであることを認識
・スクリーンショットなど外部持ち出しは最小限に
④ 記録・証跡
・個人間でのLINE内のやり取りは形式的証跡として提出は難しい
・参加者一覧や削除履歴の確認で管理責任を明確化
________________________________________
3. 行政・監査のポイント
・形式上の懸念:個別LINEは、個人端末依存のため、「正式なログ」としては扱えない
・現場運用での安全性:グループLINEは、参加者一覧確認+退職者即時削除で、情報漏洩リスクはほぼゼロ
・対応策:行政や監査で形式的安全性を求められた場合は、法人用システムを補助的に使用することも可能
________________________________________
4. 現場でのメリット
・利用者の好みや傾向を職員間でスムーズに共有
・報告・相談のハードルを下げ、質の高い支援を維持
・新規職員でも早く業務に慣れやすい
________________________________________
5. 注意点
・人材確保・職場環境改善等事業補助金や処遇改善加算については、**「現場での課題洗い出しや計画立案の段階でも算定可能」**と明記されている。
※ICT導入補助金や雇用・労働業務改善助成金等は今回の運用には直接関係しない。
・定期的に運用状況を確認し、必要に応じて改善策を導入
________________________________________
💡 まとめ
LINE運用は現場改善に十分有効。行政や補助金の形式要件も補助策で対応可能。「現場効率」と「形式上の安全性」の両立を意識した運用が鍵。
【この資料の活用例】
・現場会議で付箋やホワイトボードと組み合わせて使う
・人材確保・職場環境改善等事業補助金の申請書作成に添付する
・新人研修や内部研修で「課題把握〜解決までの流れ」を説明する教材に
【注意事項】
・本資料は参考用であり、必ずしも行政の判断を保証するものではありません。
・現場に合わせてカスタマイズしてご利用ください。
補足と結論
人材確保・職場環境改善等事業補助金や処遇改善加算については、「現場での課題洗い出しや計画立案の段階でも算定可能」と明記されている。
※2025年度に関しては、「解決するべき課題を決めよう」までで終わっている。
そして「※一度に全て解決しなくてよい」と明記されている。
これは、
=「現場での課題洗い出しや計画立案の段階でも算定可能」
という意味である。
よって人材確保・職場環境改善等事業補助金や処遇改善加算については、LINEに限らず『何かしらの通信手段を検討した』としただけでも、今回は認められる。
まとめ
上記のことから、あまり固く考えずに一旦柔軟に考えてほしいという行政側の意図が見えたので、私は素直に現場の職員に『気になる事』や『困っている事』等がないか聞いてみました。結果今回の意見が出てきました。
私はこれらの意見を聞いて、職員たちの意向としては『もっと質の良いサービスを提供したい』『そのためにはもっと情報が必要だ』『訪問職員は孤独になりやすい、相談相手が欲しい』『この相談は取るに足りないと思われるかもしれない(相談していいのか、どうしても迷ってしまう)。』色々な思いを感じ取りました。
まぁ私自身サービスに入るし他事業所での経験もあるので痛いほどわかるのですが、やはり『サービスの質の向上』を考える職員が圧倒的に多いですね。
他の意見も、もっと出ると思いますが本質は変わらないような気がしています。具体的に解決する為に、もっと意見は出てほしいですね。また機会があれば、コメントで教えていただけたらなと思います。
やってみた感想
私は施設勤務の経験もありますが、圧倒的業務量に押されて、誰が誰なのか把握することすらままなりませんでした。
この計画には載せきれない個性の把握は、一対一で対応する訪問サービス特有のものかもしれません。一対一でしか見えてこないものがそこに確かにあります。業務の洗い出しにより、役割が分担できれば在宅にこだわる必要もなくなってくるのかもしれませんね。
でもまだまだ課題はありますよ。食べたい気分じゃないメニュー、差し入れの制限、面会・外出の記録、これら縛りがある施設で私自身はそこで暮らしたいとは思えません。
最近は柔軟になりつつありますが、これらは施設側のリスクマネージメントと単位の算定上緩和が非常に難しいので、実質本当の意味で好き勝手出来るのは自宅だけです。
私としては、施設が家になりえる事は絶対あり得ないと思っているので、この訪問介護という仕事を選びました。
私が見える範囲。私と関わる人は、自分の人生に悔いなく生きてほしいと思ったから。
以上、長々と失礼しました。
▶前編での課題の把握。実際のやり取りはこちら
これらの参考資料が、あなたの役に立てれば嬉しいです。