仁義なき戦い 〜スリッパ編〜
足を負傷して松葉杖生活になったある日、私はスリッパを履かずに移動していた。
そこに現れる弟・しょーくん(知的障害を伴う自閉症)。
「おねーちゃん!スリッパ!」
そう言って、私の足元にスリッパを置く。
「まだ履けないの。松葉杖だから」と伝えると、
「松葉杖かー」と納得したような、してないような顔で、スリッパを部屋の隅に置いて去っていった。
……が、数分後。
「おねーちゃん、スリッパ!履く!」
また持ってきた。
それからは、トイレに行こうと立ち上がるたび、スリッパが召喚される日々。しかも置き場所が毎回変わっている。まるで将棋の駒のように位置を変えるスリッパ。
最終的に私は、その“隠し場所”にうっかりつまずきかけ、治療期間が延びる危機に瀕した。
こうして「スリッパ攻防戦」は足が治るまで続いた。
…地味にストレス、地味に危険、そして地味に笑える。
弟を理解するために使った「介護過程」
私は介護福祉士。弟の行動の背景を理解するために使ったのは、職場でも使う「介護過程」という専門的なプロセスだ。
介護過程とは、簡単に言えば
“その人のことを科学的に分析し、理解し、支援するための手順”
である。
本来は利用者さんにどんなサービスが必要かを計画し、実施し、評価していくためのものだけど、家族理解にも応用できる。障害児がいるご家庭にも実はおすすめだ。
実際にやってみた「スリッパ事件の介護過程」
- アセスメント(情報収集)
弟は優しい性格で、ルールにこだわりが強い自閉症の特性があります。特に「室内ではスリッパを履く」というルールへのこだわりが強く、コミュニケーションは限定的ながらも、行動で気持ちを示す傾向があります。 - 分析・課題抽出
弟はルーティンを崩したくない気持ちと、姉の安全を願う気持ちからスリッパをすすめている。しかし松葉杖の使用期間には、スリッパが転倒リスクになっていることを理解していない。 - 計画立案
弟の気持ちを尊重しつつ、安全を確保するための代替案を検討。松葉杖期間中はスリッパを履かないが、スリッパを持ってきてくれたことに感謝を伝える。代わりに安全な履物を探すなどの工夫も検討。 - 実施
「今は履かないけど、ありがとう」と感謝を伝える。スリッパは安全な場所に一時保管。弟の理解を深めるために繰り返し説明を行う。 - 評価・見直し
弟の満足度はおおむね保たれており、転倒は回避できている。スリッパのサプライズ登場は少し減ったが、まだ続いているため、次の一手が必要。スリッパの代わりになるものを探し、怪我の治りを待ちながら、今後は弟が納得できる新しいルールづくりを進めていく。
家族にこそ役立つ「介護過程」、でも家族だから難しいこともある
職場でなら、私は冷静に介護過程を回せる。でも家族は24時間モード。自分を消してずっと合わせるのは正直しんどい。時には「やめろー!」と叫びたい夜もある(笑
職場なら淡々とできる分析も、家族だとつい感情的になる。でもあえて“介護過程モード”に切り替えると、弟の行動が「嫌がらせ」ではなく「彼なりの善意」に見えてくる。
「ああ、これは彼なりの“姉を守る計画”なんだ」と…
…まあ、守られてる感より攻められてる感の方が強いけど。
…ま、まぁ、その善意は物理的に危険なんだけど。
まとめ
介護過程は、職場だけでなく家庭でも応用できる“人間理解のツール”だ。
特に、予測不能な行動をする家族がいる場合、怒るより先に「分析モード」に入れるので、心の平和を保ちやすい。
ただし、どんなに分析しても、スリッパ攻防戦は避けられないこともある。
今日もまた、仁義なきしょーくんとの戦いが幕を開ける——。
ご覧いただき、ありがとうございました。
ご意見・ご感想をお待ちしています。
次回
障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編)
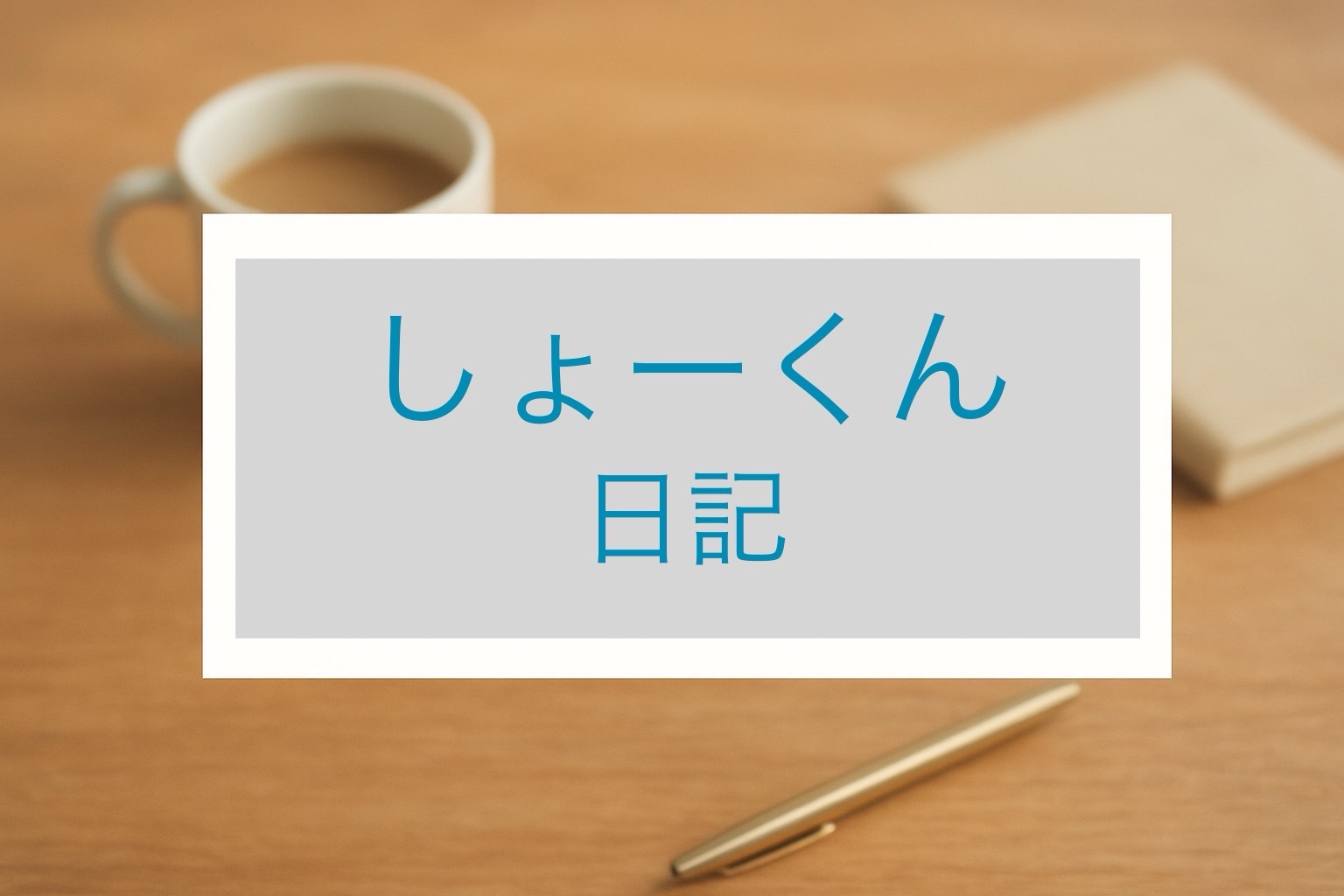

コメント