【第3章】「声を上げると、不利益になる」
弟の就労先である就労継続支援B型の作業所では、支援と称した行為が時に本人の尊厳を奪うことがあります。
特に「身体拘束」という言葉は、高齢者介護や医療の現場で耳にすることが多いですが、障害福祉の現場にも存在します。
本来、身体拘束は「緊急性」「非代替性」「一時性」という三原則を満たす場合に限定されています。
しかし、現場ではその原則が形骸化し、日常的に行われるケースもあるのです。
中編では、弟が経験した具体的な事例を通して、制度と現実の乖離を掘り下げます。
「選択の自由」は、ほんとうに自由なのか
障害福祉の現場では、本人や家族が「合わない」と感じたとき、選択肢はあるようでいて、実はとても狭い。
そして声をあげた結果、別の場所を探すしかなくなる。
──そんな現実もあります。
本来なら場面に適していない対応を受けても、
「抗議しても、環境がよくなる保証はない」
「むしろ、波風を立てたことで冷遇されるかもしれない」
「通い続けるには、今の場所しか現実的に選択肢がない」
──そう考えると、結局は何も言えなくなる。
B型作業所は「支援」が主眼に置かれているはずなのに、利用者本人よりも、施設運営側の都合が優先される場面が多々ある。
支援の現場であっても、いや、支援の現場だからこそ、「異議申し立て」が許されない空気がある。
「別の事業所を選ぶ自由」は制度上は保障されています。
けれど実際には、「うまくいっていないから他を探す」とは、そう簡単には言い出せません。
私自身も、弟の通う事業所で支援の内容にどうしても納得がいかず、改善をお願いしたことがありました。
しかし、対話を重ねた末に送られてきた文書には、こう記されていました。
「ご家族様が事業所の方針や対応にご納得いただけない場合は、他の福祉サービスや事業所への移行も選択肢の一つとしてご検討ください」
それは、施設からの「これ以上の対応は難しい」というサインでもありました。
一見、自由な選択があるように見えても、実際には「退所を促された」と感じる人も少なくありません。
支援の中で、本人や家族が声をあげることにリスクが伴うとしたら──。
制度の理念そのものが、届くべきところに届いていない証なのかもしれません。
「ありがたく思え」「感謝しろ」
──そう言われているような空気。
実際、私が支援に対して疑問を投げかけたとき、誰も真正面から答えようとはしなかった。
ただ、
「施設の方針なんです。ご理解ください。」
「間違っているのは分かっています。」
「家族さんが正しいんですけど、すみません。」
──そう言ってくれる職員もいた。
でも、その声が施設全体の方針を変えることはなかった。
現場スタッフは家族の提案に前向きである一方で、上層部が許可を出さずに制度的・管理的な壁になっている。
その壁が制度的な人員配置基準の問題か、あるいは上層部の心理的な拒絶感(「言いくるめられた」感)によるものか…
おそらく現場の職員も、私たちと同じように“言えない立場”だったのだと思う。
誰かひとりが異議を唱えたところで、上層部の意向には逆らえない。
家族として「違和感がある」「納得できない」と感じたとしても、それを示した瞬間に、“ここにいられなくなるかもしれない”という恐れが現実になる。
職員も、家族も、声を上げづらい。
そんな空気が、確かにそこにあった。
支援の本質は、家族や本人が「文句を言わない」状態を保つことではない。
本来は、「よりよい支援」を一緒に考える姿勢であるべきだ。
でも、今の現場にはその余裕がない。
職員も、人手不足や制度疲弊の中で必死にやっている。
だからこそ、「異議を言う人」は“面倒な人”と見なされる。
訴える手段があるようでいて、どこにも通じていない──そんな手詰まりを、私は何度も味わった。
私は一度、就労継続支援B型事業所の開設を検討したことがある。
でも、私の住む市では「既に事業所が飽和している」とされ、新設は却下された。
・・・飽和しているとは、なんだろう?
『送迎をしてくれるところか、親が送迎しなければならないところか』
『弁当持ちか給食か、昼食は誰が作るのか』
そして何より本当の理由
『事業所の方針と合わないから、事業所を変えたい』
・・・これを言って、果たして別の事業所が受け入れてくれるのだろうか。
“きっと、面倒くさい保護者だ、受け入れるのにはリスクがある”と判断し、受け入れてくれないであろう。
そもそも弟は自閉症だ、環境の変化に耐えられるだろうか。
・・・飽和しているとはいえ、これじゃ、行ける所なんか、ないじゃないか。
選択肢がない。
声も届かない。
それが、今の福祉の一端なのかもしれない。
【第4章】制度の変化と、包摂のかたち
制度が変わろうとしている。
「移行」「成長」「一般就労へのチャレンジ」──その流れは必要だと思う。
今は、昔と違って早期療育も広がり、障害児の中にも高い力を発揮できる子が増えてきた。
軽度の知的障害やグレーゾーンの子どもたちは、昔なら通常学級にいたかもしれない。
けれど今は、より専門的な支援を受けるために、特別支援学校を選ぶことも増えた。
それは「包摂の後退」なのか「適切な支援の前進」なのか。
私個人としては、後者だと思いたい。
なぜなら、人は死ぬまで精神的に成長できる。
弟も、移行には至らないものの、日々小さな成長を重ねている。
ただし、制度が「評価しやすい人」に偏り、「評価しにくい人」を置き去りにすることは避けなければならない。
B型では、確かに限界もある。
でもそこは、「働くことを諦めない」ための場所でもある。
もし制度の整備が進む中で、その場所が「移行できない人の最後の居場所」として扱われ、徐々に予算や支援の対象から外れていくことがあれば、それは社会の責任放棄だと思う。
弟が今日も、黙々とテープ貼りをしている。
その姿を、社会はどう見るのか。
私たち家族は、これからも問い続ける。
次回
就労継続支援B型の未来に、不安と願いを込めて【後編】
──「移行」だけではない未来像を
【第5章】制度は誰のためにあるのか
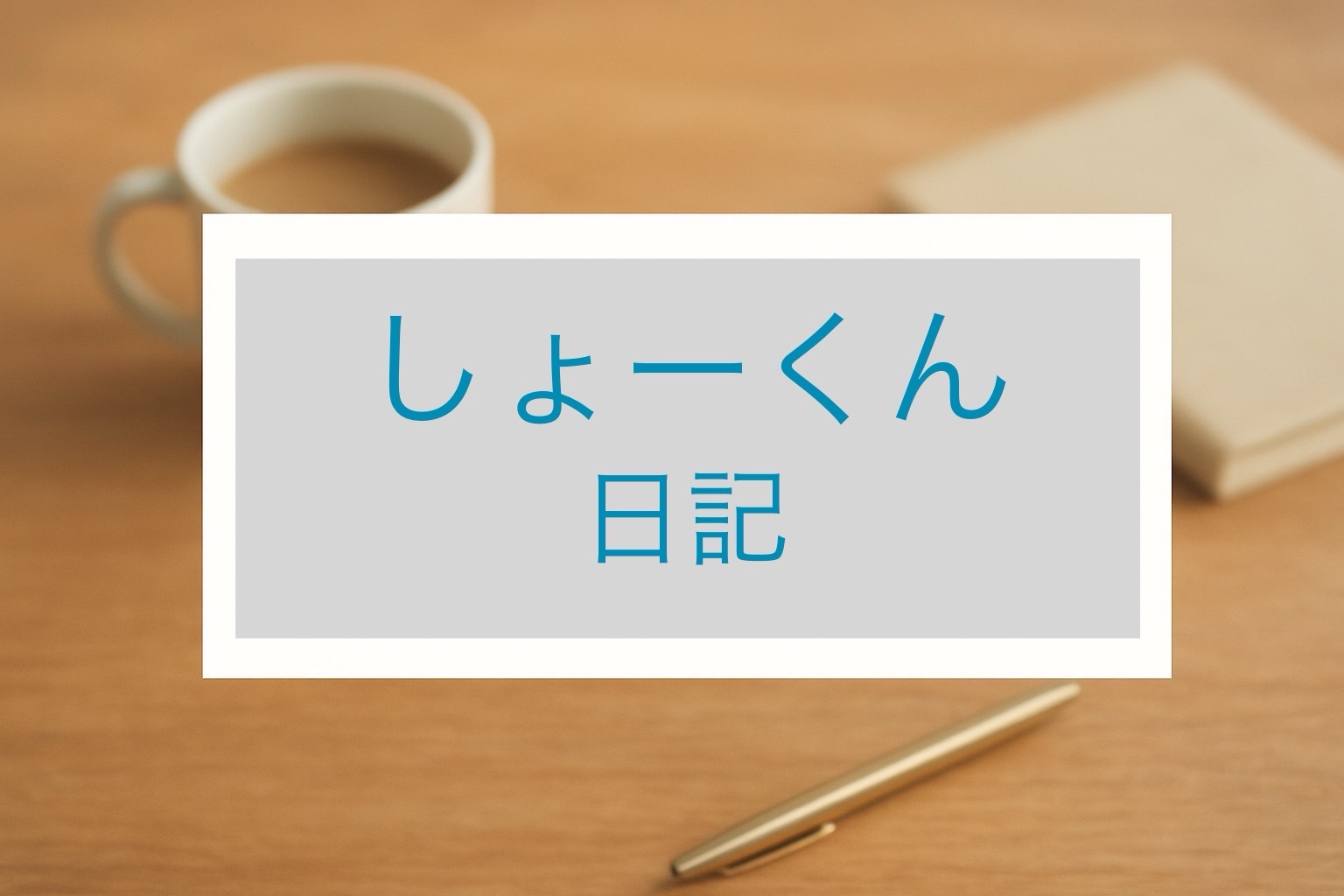

コメント