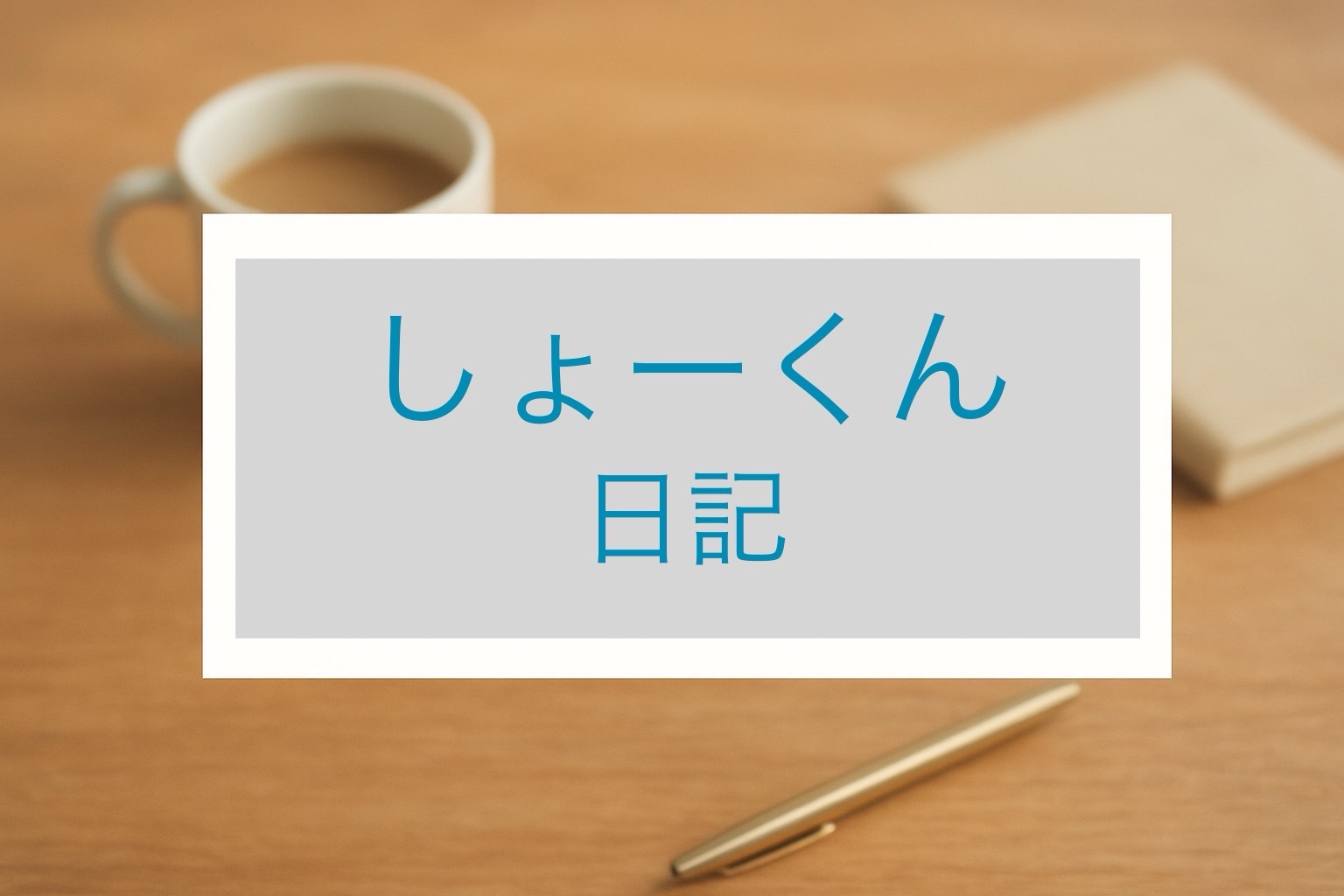支援現場では、本人のこだわりや意向を尊重しつつ、支援者や周囲の安全も確保することが最優先です。
今回の事例では以下の状況が整理できます。
今回は、しょーくんのケースを例に、段階的支援の理論を活用しながら説明します。
事例の整理
支援の現場では、本人のこだわりや意向を尊重しつつ、支援者や周囲の安全も確保することが重要です。
今回の事例では、次の状況が整理できます。
- 姉は足を怪我しており、スリッパを履くと転倒リスクが上がる
- しょーくんは姉にスリッパを履いてほしいという意向を持つ
- しょーくんはスリッパを姉の足元に持ってくる行動をとる
その結果、姉の転倒リスクがさらに高まっている。
この状況を安全かつ学習効果のある支援に変えるためには、
ABA(応用行動分析)やABC分析、代替行動の差別強化(DRA)などの理論が活用できます。
1. ABC分析で行動の背景を理解する
まずはABC分析で、しょーくんの行動を整理します。
- A(Antecedent/先行条件):スリッパが目の前にある、姉が座っている
- B(Behavior/行動):スリッパを姉の足元に持ってくる
- C(Consequence/結果):姉の転倒リスクが上がる、支援者が制止する
ABC分析により、行動が意図的な支援行動(姉にスリッパを履かせたい)として現れていることが分かります。
一方で、行動結果として姉の安全を脅かす状況が生まれているため、行動の修正が必要です。
2. ABA理論と段階的支援の活用
ABAでは、行動を環境との関わりで学習と捉え、段階的に望ましい行動を増やすことが基本です。
今回のケースでは、目標行動を「姉の安全を守りながら、代替行動を自分で選べること」と設定します。
段階的支援の考え方
- スリッパを姉の足元に直接持っていかないことを促す
- 安全な位置に置くことを学ばせる
- 代替行動(例えば、スリッパを棚に戻す、指定の置き場所に置く)を自発的に選ぶ
各ステップを小さく設定し、成功体験を積み重ねて強化する。
これにより、しょーくんは「姉を助けたい」という意向を尊重しつつ、安全な行動を自発的に選べるようになります。
3. 代替行動の差別強化(DRA)
DRAは、望ましい行動を強化することで問題行動を減らす手法です。
しょーくんの場合
- スリッパを姉に直接持っていかず、安全な場所に置く行動をほめる
- 指定の棚やボックスに戻すなどの行動をほめる
このように、行動そのものではなく「自分で選んだ安全な行動」を強化することで、問題行動の減少と学習が同時に進みます。
4. タスク分析による安全ステップの分解
複雑な行動は小さなステップに分解すると、安全に導きやすくなります。
例
- スリッパを手に取る
- 姉の足元に運ばず、安全な位置に置く
- 代替行動(棚に戻すなど)を自発的に選ぶ
このステップを少しずつ習得することで、しょーくんは姉を助けたい気持ちを満たしつつ、姉の転倒リスクを下げる行動を学べます。
5. ポジティブ行動支援(PBS)の視点
PBSでは、支援者や環境を整えながら、本人の尊厳を守ることが原則です。
- しょーくんの「姉にスリッパを履かせたい」という意向を尊重
- 安全な代替行動を選ぶことを学習させる
- 環境を整えて、転倒リスクを下げる
これにより、本人も支援者も安心して日常を過ごせます。
6. まとめ:理論に基づく安全な支援
段階的支援を意識することで、しょーくんは自分で安全な行動を選び、姉の転倒リスクも減らすことができます。
大切なのは、無理に行動を変えさせるのではなく、本人の気持ちを尊重しながら小さな成功体験を重ねることです。
毎日の観察や簡単な記録を通して、少しずつ安心できる環境をつくり、安全で学びのある支援を積み上げていきましょう。