こんにちは。あーちゃんです。
私は「きょうだい児」として育ちました。障害のあるきょうだいを持ち、家族の一員として支える日々の中で、いつも「自分は後回しでいい」と無意識に思い続けてきました。周囲からは「えらいね」「優しいね」と言われることもありましたが、それがどれだけ自分を縛る言葉だったかを、今になって痛感します。
大人になった今、私は福祉の仕事に就いています。弱い立場にある人のそばにいたいと思ったからです。でも、そこで見えたのは、ケアを担う側があまりにも低く見積もられているという現実でした。
介護職は低賃金で、地位も社会的評価も極めて低い。
たとえば、訪問介護。これは在宅での生活を支えるインフラであり、家族だけではとても担いきれない役割です。
訪問介護員は施設介護とは違う部分での専門性があるにもかかわらず、制度の中でも、施設介護よりも軽く扱われています。
私は思うのです。
私たちは本当に、「家庭の問題」や「情の世界」で福祉を語り続ける社会で良いのか、と。
誰もが必要になる介護。
それを支える人が、経済的にも精神的にも報われない社会に、未来はあるのか、と。
政治の場でこの問題を口にする人は決して多くありません。ですが、どうか、現場の声に耳を傾けてほしいのです。
今の制度のままでは、志ある人材は次々に離れていきます。
もし、介護職に専門性を認め、所得税の軽減や報酬改善、職責に対する公的評価がなされるならば、介護の未来は変わるはずです。
「やりがい搾取」ではなく、「やりがいと誇りが両立する」仕事に。
これだけ社会に貢献しても、介護職はいつまでたっても報われない──
低報酬・低評価・少ない手取り。
人の尊厳を支える、専門性の高い仕事であるにもかかわらず、世間の理解はまだまだ乏しいのが現実です。
給料が上がっても、手取りがほとんど変わらない。
評価も名誉も得られず、達成感さえ薄れていくなかで、介護職が「使い捨ての駒」のように扱われる現場に身を置いてきました。
それでも、私たちは誰よりも「老後」や「障害」、そして「社会の限界」と向き合ってきました。
老いは必ず訪れます。障害も、誰にとっても他人事ではありません。
それなのに、日本社会にはまだ“当事者意識”が根付ききれていないように感じます。
介護は長らく「家族が担うもの」とされてきました。
この歴史の延長線上で、いくら専門性を磨いても、介護職が正当に評価されることは難しいのかもしれません。私は今の日本のあり方を見て、そう思わずにはいられません。
人の価値観や社会意識は、そう簡単には変わりません。
でも、せめて介護職員が“公務員”のような安定した立場で働けていたなら、ここまで軽視されることはなかったのではないか──そう考えることがあります。
実際、スウェーデンやドイツなどの国では、介護職は十分な賃金水準が確保され、社会的にも高く評価されています。
だからこそ、日本でも「介護に真剣に向き合ってきた人が受けられる税控除や将来保障」といった、具体的な支援制度があってもよいのではないでしょうか。
私は、きょうだい児として、福祉職として、社会に対して言いたい。
“誰かの家族”にすべてを任せないで。
“誰かの善意”に未来をゆだねないで。
国家の責任で支える社会へ、今こそ変えるべきだと。
このブログでは、私の体験(利用者家族・福祉職・事業所経営者という立場)を起点に、訪問介護の現場やB型作業所など色々な場面で感じてきた課題をシリーズで掘り下げていきます。。
制度の矛盾だけでなく、現場で生まれる関係性や、ケアの中で交差する感情や葛藤も含めて、等身大の言葉で綴っていきたいと思います。
導入編である今回は、その出発点としての「問題意識」を共有します。
【おすすめ記事リンク】
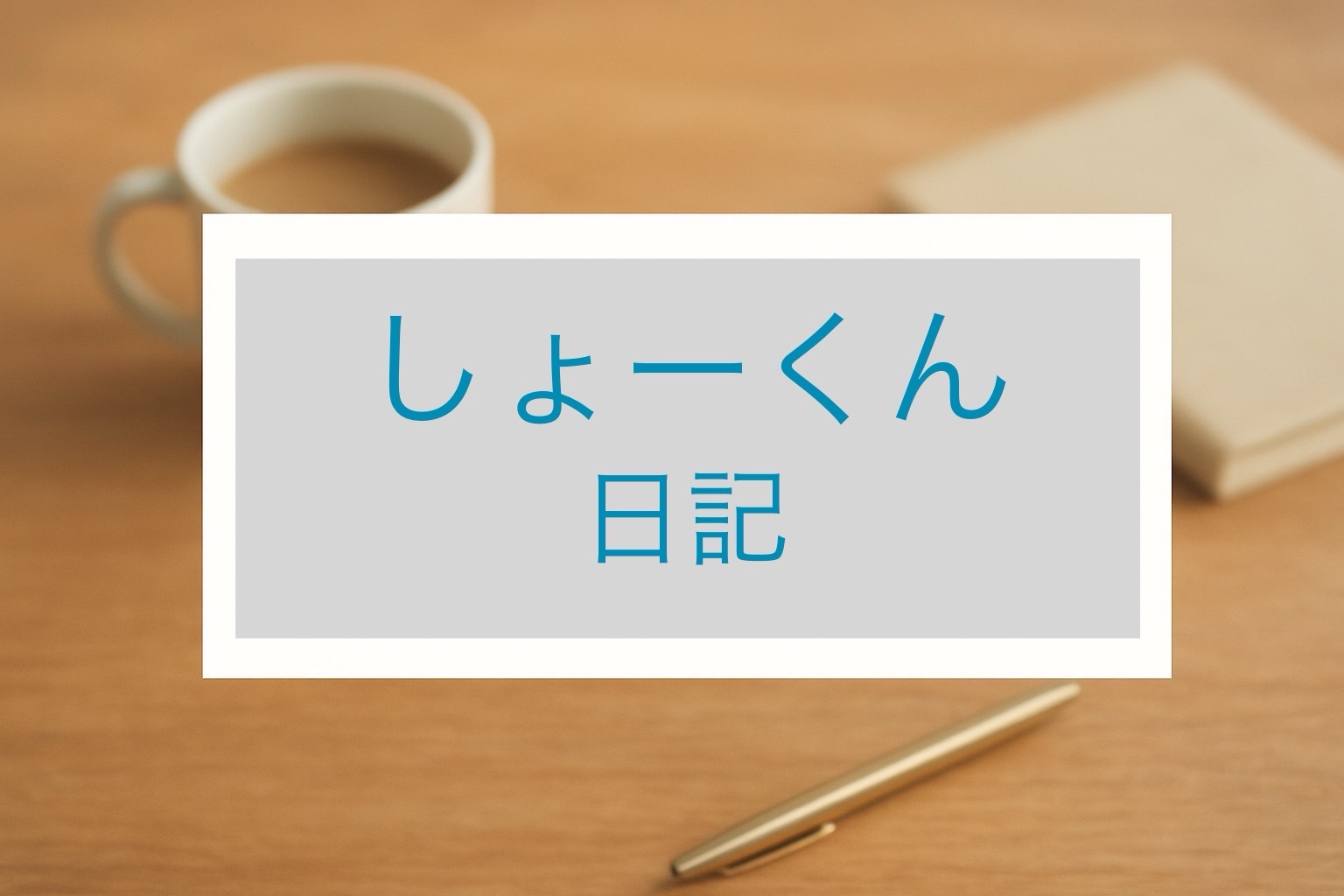

コメント