※当ブログは記事中にPRを含む場合があります
本が導いた自己理解と介護の力
私は、きょうだい児として、障害や特別な支援を必要とする『きょうだい』と共に成長してきました。家族の中で感じる複雑な思いや葛藤は、言葉にするのが難しく、ずっと心の中で抱え込んでいたものです。
しかし、福祉の専門学校で介護について学び始めたとき、手にした教材や参考書が私の支えとなりました。
そこには、家族の気持ちや専門職としての支援の考え方、解決に向けての具体的な方法が整理されて書かれており、私がこれまで漠然と感じていたことが、はっきりと言葉になっていたのです。
「自分の考え方は間違っていなかった」と心から安心でき、深い感動を覚えました。これは、私にとって本がもたらす力を実感した最初の体験でした。
この記事では、そんな私が介護を学ぶ中で特に支えられた教材・本を、ランキング形式で紹介します。
きょうだい児としての自己理解を深めたい方や、介護・福祉の仕事に関わる方の参考になれば幸いです。
印象に残っている教材ランキング
きょうだい児としての経験を原点に、介護の学びを支えた教材をランキング形式で紹介。
支援者としての視点や自己理解のヒントも満載。
介護福祉士養成講座 中央法規の15巻全部!!
…と、言いたいところですが、それだとランキングにならないので、無理やり選びます。
正直、中央法規の介護福祉士養成講座は、15巻の中から選ぶのが困難なレベルでぎゅっと詰まっています。
支援だけではなく、自立とは何か。個人が幸福に生きるとはどういうことかを学びました。
第一位
中央法規発行の**コミュニケーション技術**
何のためにコミュニケーションをとるか。コミュニケーションの必要性とは。
言語・非言語、傾聴、共感、自己開示、質問の種類・技法、同意の得る技法、意向の把握の仕方・調整の仕方、意欲の引き出し方。記録の書き方。障害等に合わせたコミュニケーションの取り方等。
これらのコミュニケーションのすべてが入っている1冊です。
興味のある方はこちらから購入できます:
自己理解・他者理解が深まるので、介護にかかわらず応用が利きます。
第二位
著者:水野敬也(みずの・けいや)の**夢をかなえるゾウ**
意外ですよね?これ、福祉学科の教材として授業で購入したんですよ。
しかも、しっかりコレを基に、将来のなりたい姿を作成しました。
個別の計画を書くのに、本人の意向が一番大事になります。
だから、これが教材になったのかな。
支援者として必要なマインドだけでなく、私個人にも良い刺激になりました。
万人にオススメ。
夢をかなえるゾウは、先にゴールを決める必要性や、継続性を実践的に学べます。
興味のある方はこちらから購入できます:
5冊まとめてほしい方はこちら
何から始めたらいいか分からない人にオススメ。
第三位
中央法規発行の**発達と老化の理解**
様々な発達段階説から、サクセスフル・エイジング(良い老い方)とは何か。
老いや障害に対し、価値転換によるポジティビティなど、生き方についての考えを整理するのに役立ちます。
興味のある方はこちらから購入できます:
老いも発達の一部です。人間は死ぬまで発達(成長)します。
私は、支援の方針に悩んだ時に読み直しています。
第四位
ミネルヴァ書房発行の**ソーシャルワーク入門**
この教材は、相談支援者のあるべき姿。
支援を必要としている人に対しての基本姿勢と関係構築方法について解説されています。
相談支援の実践原則を元に、原則の意味と必要性が丁寧に解説されています。
傾聴の仕方や受容のプロセス、共感と同情・理解の違い、利用者や家族の強みは何か。ストレングス支援とは何か。バイスティックの7原則とは。
本人や家族に対して、現場での判断や対応を考える上で非常に参考になります。
興味のある方はこちらから購入できます:
人とのかかわり方・考え方の指標です。
第五位
中央法規発行の**介護の基本Ⅱ**
社会福祉士及び介護福祉士法の中身や、倫理判断のポイントや必要性、職業倫理について。
また、施設だけでなく在宅のサービス等の解説、介護福祉士の役割に関してぎゅっと詰まった1冊です。
介護職の事が、よく分かる様になります。
興味のある方はこちらから購入できます:
支援のあるべき姿が、わかります。
番外編
恐らく今廃盤になっている2冊も内容が素晴らしかったので紹介。
①メヂカルフレンド社発行の**最新介護福祉全書11 障害の理解**
専門学校で購入した教材の中で、特に印象に残っているのはこの教材です。
正直1位だったんですが、どうやらメヂカルフレンド社さんは、今は看護教材がメインで、もう介護関係の書物出していない様なのでコチラに・・・。
この教材は、家族の心理や支援の方法が丁寧に整理されており、私の経験を振り返る助けになりました。
喪失とは何か。立ち直る方法は何か。どう生きるのか。具体的に何に困るのか。
具体的な事例が豊富で、現場での判断や対応を考える上で非常に参考になりました。
②メヂカルフレンド社発行の**最新介護福祉全書7 介護過程**
専門学校で購入した教材の中で、今も使っているのが、この教材です。
この教材は、記録やアセスメントの方法が丁寧に整理されており、実際の介護現場での経験を振り返る助けになりました。
具体的な事例から、観察したことを、どの様に記載し検討していくのか。
現場での判断や対応を考える上で、非常に参考になります。
支援者側が本を読む意義
介護福祉士として現場で働く今も、本は私にとって自己研鑽の大切なツールです。
現場では、利用者や家族の気持ちに寄り添うだけでなく、専門知識や方法論に基づいた支援を提供することが求められます。
専門学校で学んだ理論や、本で得た知識は、自分の経験を整理し、より質の高い支援につなげる手助けとなっています。
例えば、家族の心理を理解するための書籍を読むことで、自分自身のきょうだい児としての経験を振り返り、共感力を深めることができました。
認知症ケアや高齢者福祉の専門書は、現場での判断や対応の参考になり、理論と実践を結びつける道標となります。
利用者側が本を読む意義
本を読むことで得られる効果は、単なる知識の取得にとどまりません。
私にとっては、自分を理解し、救われた体験でもあります。
きょうだい児として抱えてきた心の葛藤や不安は、福祉の学びや本を通じて整理され、自分の感情を肯定する力につながりました。
専門学校の教材や介護関係の書籍は、同じような立場の人々や、支援を必要とする家族の気持ちを理解する手がかりを与えてくれます。
それは現場での実践に直結するだけでなく、精神的な支えにもなるのです。
本を読む効果
さらに、本は考えを整理し、新しい気づきを得るためのツールとしても機能します。
文章を読み、理解し、咀嚼する過程で、論理的思考や問題解決力が鍛えられます。
現場で迷ったとき、「なぜこの対応が適切か」「より良い方法はないか」と振り返る際、本で学んだ知識が判断の基準となります。
また、異なるジャンルやテーマの本を組み合わせて読むことで、介護の枠を超えた新しい発想や創造的な解決策も生まれます。
これは日常の支援だけでなく、自己成長や専門性の向上にもつながります。
私が学んだ本の中には、家族の心理を丁寧に掘り下げたもの、認知症や高齢者ケアの具体的手法をまとめたもの、介護制度や社会の仕組みを解説したものがあります。
それぞれが異なる角度から、現場での判断力や共感力を高めるヒントを与えてくれました。
きょうだい児として抱えてきた経験を知識と結びつけることで、私は自分の経験を活かしつつ、より質の高い支援を提供できるようになったのです。
まとめ
結論として、本がもたらす力は、単なる知識の取得にとどまらず、視点を広げることや自己成長、感情の理解、考えの整理、そして行動への変化という形で現れます。
本を通じて学ぶことは、現場での支援や自己研鑽を深めるだけでなく、自分自身の経験や感情を肯定し、心の支えになる体験でもあります。
私はこれからも本に触れ続け、学びを深め、現場での支援や自己成長に活かしていきたいと思います。
そして、同じ立場や職業の方々にも、本がもたらす力を感じてもらい、自分自身の学びや成長につなげてほしいと願っています。
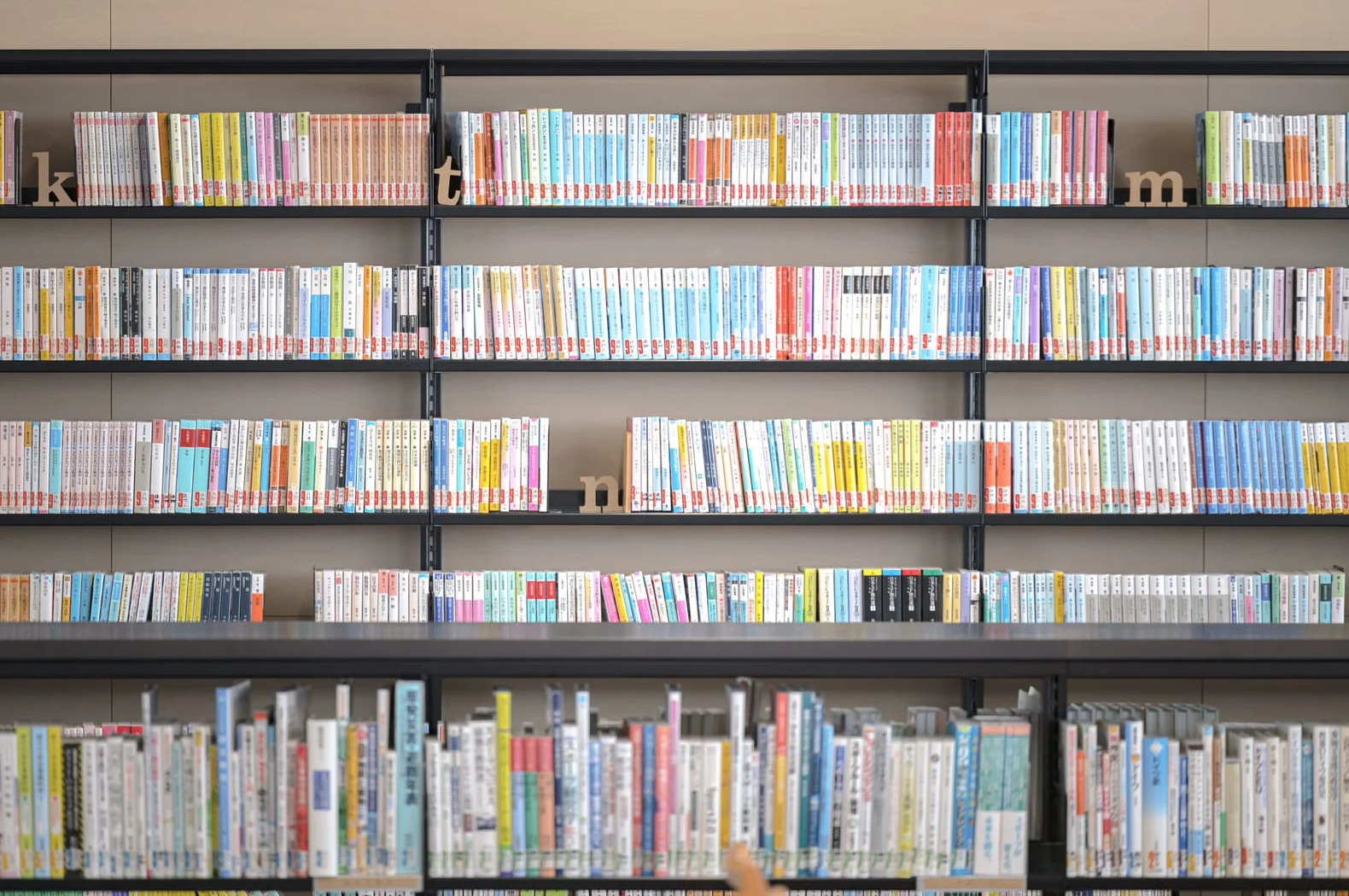


コメント