【第1章】制度の静かな変化
就労選択支援が令和7年10月から実施される。
就労選択支援は、障害者本人が自分に合った就労先や働き方を選べるよう、アセスメント(適性や希望の評価)を通じて支援を行う制度である。
※令和7年10月からは、原則として就労継続支援B型を利用する前にこの支援を受けることが求められます。
私は「就労継続支援B型の作業所を、ゆくゆく制度的に縮小させるつもりなのでは」という印象を抱きました。
「生産性が低い」「賃金も上がりづらい」という現状。
厚生労働省の資料では、就労継続支援B型の利用者は、長期利用者が多い傾向があるとされている。
こうした指摘は、就労継続支援B型を「未来の手当てを見直す必要があるモデル」として考え始めているようにも受け取れる。
私はそれを読んだ時、自分の家族のことを思い返した。
自閉症と知的障害を持つ弟。効率的ではないかもしれない。
コツコツと仕事をこなすことはできるけど、社会的ルールに適応するのは難しい。
そんな弟が「性能の低い人は縮小される範囲に入る」ような評価の形になるのはたまらない。
弟は就労継続支援B型の作業所で、商品を完成させる能力を持ち、真面目に努力を続けている。
働くという事は、人間関係の構築や自信・経験につながる。
それを「生産性」「賃金」「移行しやすさ」だけで評価するのは、支援とは言い難いのではないか。
私はここから「仕事について」「支援について」「家族の気持ちの変遷について」自分の家族の事を書いていきたい。
【第2章】高い作業能力と感覚過敏
──「作業はできる。でも、それだけでは足りない」
「本人の意思を尊重する支援」が、なぜこんなにも伝わりにくいのか──。
障害福祉サービスの現場で、「家族が意見を言うこと」が、まるで支援を妨げる行為のように捉えられてしまうことがあります。
けれど、支援がうまくいかないとき、家族こそが最初にその異変に気づく存在でもあります。
作業所の対応に疑問を感じても、それを言語化するには勇気がいる。
特に家族の立場では、発言の“代償”があまりに重い。
私の弟は、重度の自閉症と知的障害がある。
でも、その中でも「できること」は確かにある。
たとえば就労継続支援B型作業所で、商品のテープ止めやシール貼り、大袋へのまとめ作業、物品の移動など、繰り返し型でパターンが定まった作業では、非常に高い集中力と作業精度を見せている。
実際、作業所の職員からも「作業能力は高い」と評価されている。
けれど、弟と社会には大きな壁がある。
──それが「感覚過敏」と「指示の理解」に関わる困難だ。
弟は、音に非常に敏感だ。
騒がしい環境になると、耳を押さえ動揺することもある。
また、光にも過敏で、蛍光灯の明滅や反射が強い場所では、目を細めたり、体を強張らせてしまう。
そんな弟にとって、サングラスや音楽プレイヤーは、生活の質を保つ「命綱」だった。
ところが作業所の入所当初、こう言われた。
「それはオシャレです。他の利用者がマネをしたがる。サングラスと音楽プレイヤーは許可できません。」
結果として、弟は耳栓と伊達眼鏡に変更し、その作業所に通うときだけ装備を変えざるを得なかった。
やがて時代が変わり、作業所でもサングラスと音楽プレイヤーが認められるようになった。
でも──その時にはもう遅かった。
弟は「それらを使うと怒られる」と刷り込まれてしまい、今ではどんなに許可されても、作業所では眼鏡と耳栓しか使わない。
本人のこだわり、というより、「怒られた記憶」が彼の行動を縛っている。
──弟は作業能力が高い。
でも、柔軟な対応や臨機応変な行動は苦手だ。
だから、パターンが決まっていればうまくいくけれど、少しでも予期しない変更があると混乱してしまう。
作業所側も、そうした特性を理解していないわけではない。
でも、制度の風向きが変わり、「移行」「生産性」「賃金アップ」「効率」といったキーワードばかりが踊るようになると、どうしても「扱いづらい人」=「足を引っ張る存在」とされてしまう危険がある。
実際、弟に起きた“事件”がある。
作業場の人数が増え、環境が落ち着かなくなっていたある日。
弟は騒がしい環境に我慢が出来ず部屋を飛び出した。
それまでの十数年間、一度もそんなことはなかった。
作業所の対応は「身体拘束」だった。
──逃げたことに対する“対策”として。
当時、本人の混乱があったわけでも、自傷他害が続いていたわけでもありません。
それにもかかわらず、ある日、弟は「身体拘束」という形で制限を受けました。
その後、保護者である母のもとに渡されたのは「身体拘束の同意書」でした。
書面上には“書いて差し支えのない理由”が並び、どこにも「本当の理由」は書かれていませんでした。
担当者は申し訳なさそうな表情で、現場の事情を説明した。
法的にも、倫理的にも、本来なら許されることではない。
だけど、この現場では“仕方のないこと”として処理されていった。
何よりつらかったのは、その後に渡された「説明文」に、施設長(理事長)による一筆が添えられていたことでした。
私が口を挟む余地はどこにもなかった。
この出来事について、私はいまだに納得していません。
けれど、施設側に強く異議を唱えれば、弟の居場所が奪われるかもしれない。
それが現実です。
「──声を上げると、支援は遠ざかる」
この言葉が、頭をよぎりました。
就労継続支援B型事業所は「本人の意思を尊重する支援」が原則ですが、現場でそれがどのように実現されているかというと、必ずしも単純ではありません。
実際、弟の支援内容について相談したとき、家族としてどうしても伝えざるを得ないことがありました。
本人が困っている様子を目の当たりにしていたからです。
けれど返ってきたのは、「施設の方針ですのでご理解ください」「ご家族の言っていることが正しいのは分かっています。でも、私たちにはどうすることもできません」といった言葉。
話し合いの末に送られてきた文書には、こう記されていました。
「事業所としてできる限りのサービスを提供したいと考えておりますが、ご家族様が事業所の方針や対応にご納得いただけない場合は、他の福祉サービスや事業所への移行も選択肢の一つとしてご検討ください」。
表現としては穏やかですが、「納得できないなら、他を探してください」というニュアンスがにじみ出ていました。
「自己選択・自己決定」の理念のもとにある支援現場で、声をあげれば遠回しに退所を促されるような構造。
制度の理念と実際の運用との間に横たわる、静かな分断を感じざるを得ませんでした。
──声を上げると、支援は遠ざかる。
静かに従っていないと、
「預かってもらえなくなる」
そう感じてしまう現実が、確かにそこにある。
──では、どうすれば「声を上げても居場所を失わない」支援ができるのだろうか。
次回
就労継続支援B型の未来に、不安と願いを込めて【中編】
──「選べる」はずの支援、「選ばせない」現実
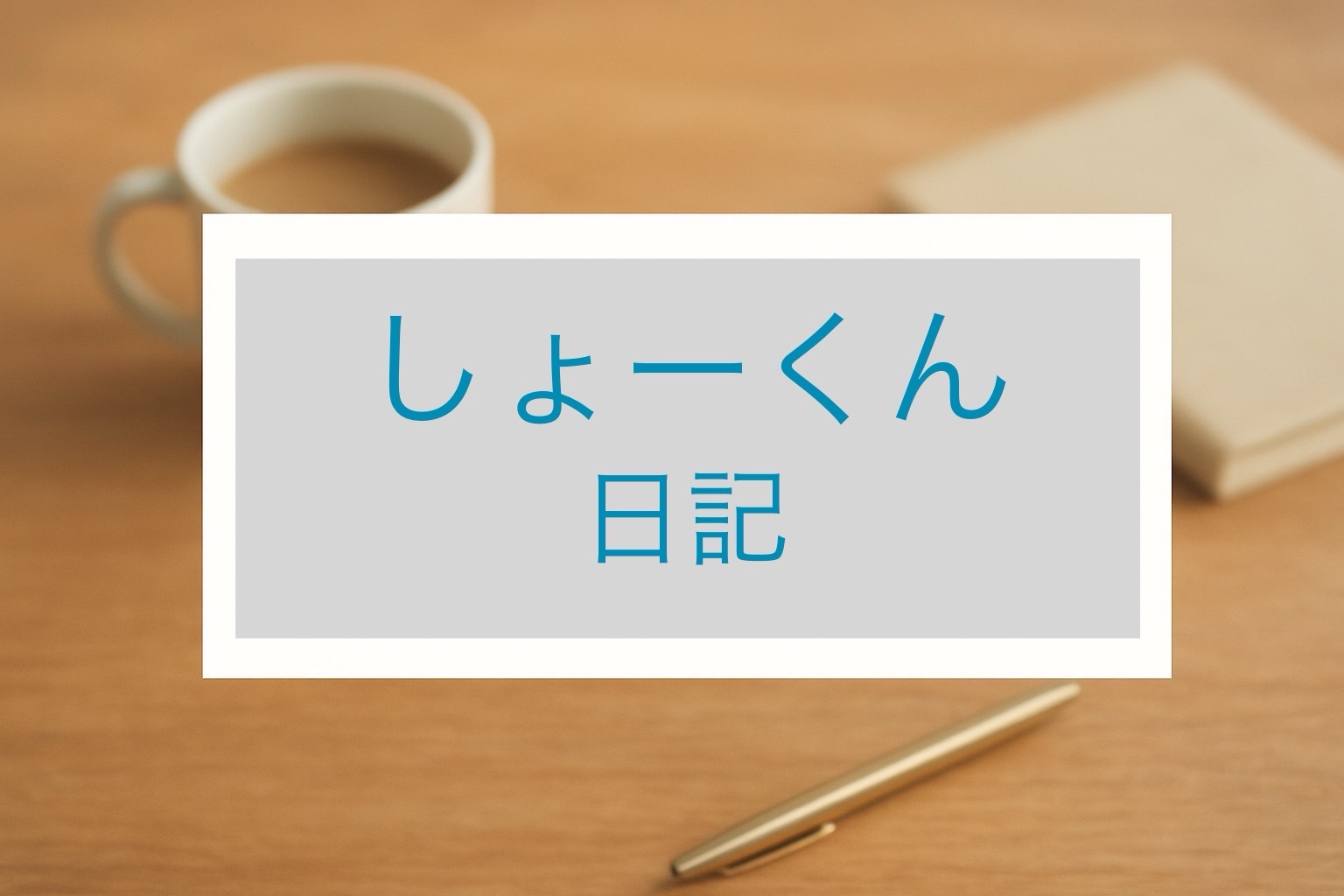

コメント