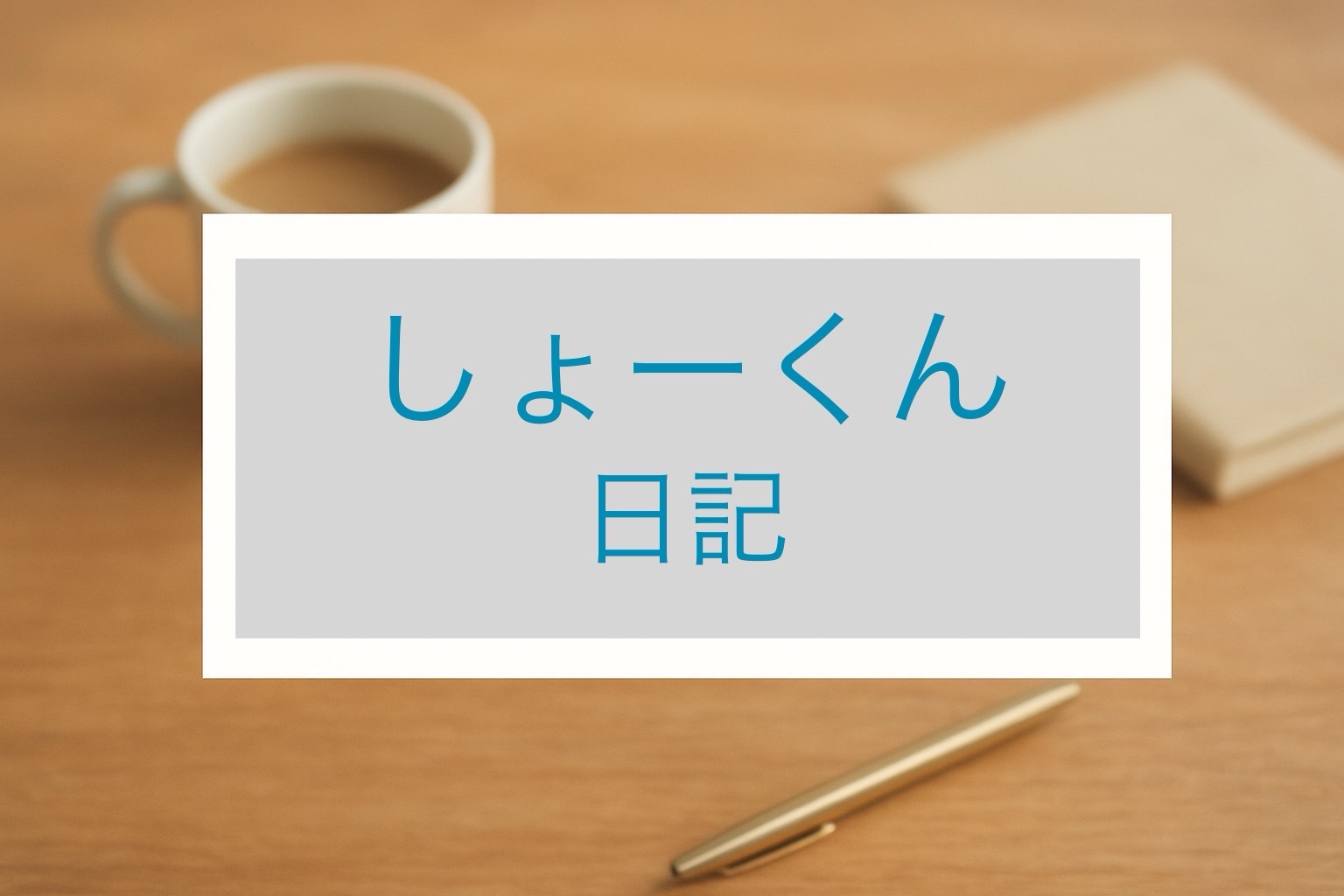最近、「強度行動障害は地域で支える」「入院は減らす」という議論がニュースで取り上げられています。
けれど、そこには本人や家族の生活・希望という最も大切な視点が抜け落ちています。
認知症も同じで、「医療費削減」だけでは語れません。
家族視点で見た強度行動障害支援の課題
家族は長期の支援で疲弊し、時には「このままでは共倒れになる」と追い詰められます。
「入院を減らす」と言われても、訪問支援や地域資源が十分でなければ家庭の安全は守れません。
入院には「休養」や「安心」を得る役割もある。
それを無視すると悲劇的な事態につながりかねません。
家族の疲弊と心理的負担
制度が「自助で対応せよ」という前提で動く場合、実質的に家族に過剰な負担がかかります。
支援を続ける中で家族は疲弊し、「このままだと家族を傷つけてしまうのでは」と追い詰められることがあります。
政策や報道で「入院を減らす」「地域で支える」と言われても、現場の訪問支援が十分でなければ家族の安全は守れません。
心理的に追い詰められる家族が増えれば、悲劇的な事態(例:心中)につながる可能性があります。
また、入院除外の理由が「治療効果が望めない」とされることがありますが、精神科入院には本人や家族の休養を目的とした判断もあります。
こうした視点が考慮されないまま制度が進められることは、家族の負担感をさらに増やす可能性があります。
現場支援とのギャップ
病院側は入院制限の方針でも、家族が追い詰められた場合には緊急対応が必要です。
「訪問看護で対応」とされても、現場が常に即時対応できるわけではありません。
制度上の安全策と現実の支援体制のずれが、家族・本人双方のリスクにつながります。
医療モデル偏重の課題
多くの議論は「治療できるかどうか」という医学的観点で線引きされがちです。
しかし、治療できないことと、生活や行動の改善可能性は別です。
人は障害や病気があっても学び、成長します。
この点を無視した議論は、本人の尊厳や可能性を見落とすことになります。
強度行動障害に対する厚生労働省の意見
厚生労働省
精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会
第9回2025年9月8日資料
PDF【資料1】精神疾患に係る医療提供体制について(その2)
めちゃくちゃ検討してくれてます。
あまりにも長いので、これをAIに要約させてみました。
国の方針はどうなっているのか?
『厚生労働省は、今後の入院医療のあり方を
「急性期」「包括期」「慢性期」の3つに整理しています。
そのなかで「地域では対応が難しいケース」として、
強度行動障害の人たちが例として挙げられています。
つまり、国も「地域に戻るのが難しい人たちがいる」ということを認めていて、
入院医療や長期的な支援のあり方を見直す必要があるとしています。
その上で、厚労省は
- 「強度行動障害=特別な病棟で囲い込むべき対象」ではない
- 入院を長期化させない体制を作ることが必要
- だから、地域包括ケアの中で受け止められるように、
福祉サービス・地域精神科医療を強化する
この方向性になっているとのこと。
家族だけの問題ではなく、社会全体の問題
強度行動障害や認知症の方の支援は、特別な家庭だけの問題ではありません。
誰でも、病気や高齢化によって「行動のコントロールが難しい立場」になる可能性があります。
もし社会が十分に支えられなければ、家族は疲弊し、医療や福祉のコストも増えていきます。
これは社会全体にとって大きな損失です。
どう支えるべきか?
家族だけに負担を押しつければ社会全体が疲弊します。
支援がなければ医療・福祉コストも跳ね上がり、結局は私たち全員に影響が及びます。
大切なのは「入院か地域か」という二者択一ではありません。
必要に応じて入院ができる体制と、地域で安心して暮らせる支援の両方が整っていることが重要です。
そのためには、
- 行動障害や認知症の方に合った支援体制の整備
- 家族の心理的・身体的負担を軽くする仕組み
- 社会全体で支える意識の広がり
が欠かせません。
支援の本質
認知症も強度行動障害も、最終的に重要なのは「どう対応すれば本人の苦痛を和らげ、生活の質を高められるか」です。
暴力や自傷などの行動は、本人が伝えられない苦痛や不安の表れです。
その苦痛を理解し、対応することで、無理に行動を止めなくても自然に落ち着くことがあります。
環境調整やルーチン、刺激の軽減などは手段であり、最終的には本人が「理解されている」「安全だ」と感じられる関わり方が、症状の安定や苦痛緩和につながります。
利用者の生活の質は、支援者や家族・社会の関わり方が左右します。
苦痛を和らげる必要性
強度行動障害や認知症の行動は、苦痛や不安のサインです。
暴力や混乱を「抑える」ためではなく、
本人が「理解されている」「安心だ」と感じられるために必要です。
薬物療法も時に有効ですが、それはあくまで補助。
基本は「環境調整」と「関わり方」です。
教育と現場の課題
支援の鍵は「行動を抑え込む」ことではなく、
「苦痛を理解し、共に安心できる環境をつくる」知識と技術です。
介護福祉士の教育では、認知症ケアについては「関わり方」「安心できる環境」の重要性を学びます。
しかし強度行動障害についてはほとんど触れられません。
ABA(応用行動分析)や行動支援計画などの科学的な方法論は、専門職向けに別途学ぶ必要があります。
そのため現場では「どう関われば行動が落ち着くか」を知らず、戸惑う支援者や家族が多いのが現実です。
さらに、無資格の障害福祉職員が支援に関わるケースも少なくなく、専門的知識や技術の不足が支援の質に直結しています。
感覚過敏・ルーチン・意思疎通への具体対応
たとえば、視覚過敏等で、眩しい光が苦手な場合は
- 照明器具を調整する
- サングラスをかける
- 光の少ない場所に移動
逆にこだわり方で、どんな感覚器がこだわりに直結しているのかも見えてきます。
例えば服のこだわり1つをとっても
- 手触りや着心地であれば触覚
- 色・デザインであれば視覚
要は観察です。
聴覚過敏であれば
- イヤーマフをつける
- 音楽プレイヤーの使用を許可する
- 少人数部屋を提供する
…等が有効です。
また、このような行動が繰り返されるうちに、
安心感や落ち着きを得るルーチンになっていることもあります。
こうした背景を踏まえて、配慮した環境を整えることが大切です。
意思疎通が難しい場合でも、表情や行動から不快な原因を探ったり、
日頃からよく知っている人の知識を活用したりすることで、
苦痛の特定は十分に可能です。
感覚過敏やこだわりが複合的に絡み合っている場合でも、観察と対応を重ねることで、本人が安心できる環境を作ることができます。
医療的介入の位置づけ
支援者の工夫だけでは対応が難しく、本人や周囲の安全が脅かされる場合もあります。
その際、認知症では抗精神病薬や抗不安薬が短期的に処方されることがあり、強度行動障害でも自傷や極端な興奮が続く場合には薬物療法が補助的に用いられます。
これは決して「支援の失敗」ではなく、安全を守るための正当な選択です。
薬物療法はあくまで苦痛の軽減や生活リズムの調整の補助であり、環境調整や関わり方を主軸に支援を続けることが基本です。
認知症は高齢者医療・介護と直結しているため薬物が比較的早く検討されやすい一方、強度行動障害は若年~成人期が多く長期支援が必要なため、薬だけに頼ると副作用や支援停滞のリスクが高く、非薬物的支援が中心となります。
入院か地域かだけで語る危険
ニュースや記事で「入院か地域か」と議論されると、支援の本質が抜け落ちます。
本人が「わかってもらえている」と感じられる関わり方こそが、症状安定の鍵です。
過敏な感覚そのものは消せません。
では、どう苦痛の緩和をするのか。
- 周囲が環境整備を行う
- 本人のルーチンワークを尊重する
この2点で、本人の苦痛を軽減させ、安心して過ごせるように調整します。
医療費や施設の確保も大事ですが、本人の苦痛に寄り添い、強度行動障害の行動の背景を理解した関わり方を提示しなければ、本人の生活の質は守れません。
希望の視点
強度行動障害も認知症も、行動の改善や生活の安定は、適切な支援によって十分可能です。
人は学び、成長し続けます。
医療的介入も支援の一部として位置づけられるべきで、環境調整や関わり方をベースにしつつ、必要な場合には薬物療法を補助として活用するバランスが大切です。
入院か地域かだけで議論するのではなく、本人の苦痛をどう軽減するか。
生活の質をどう高めるかが本当に重要な視点です。
これが介護福祉士としての私の意見です。
最後に
強度行動障害や認知症の支援は「誰か一部の人の問題」ではなく、私たち全員が直面しうる課題です。
家族だけに任せるのではなく、「どうすれば苦痛を和らげ、安心できる生活を送れるか」。
その視点を中心に、入院・地域・福祉を組み合わせた支援を社会全体で考えることが、これからの日本に必要だと思います。