~介護現場での具体的行動指針~
はじめに
介護現場で働く職員は、利用者の笑顔や自立を支えることで得られる達成感や、他者に貢献できる喜びを感じることができる魅力的な職業でもあります。
自己覚知(自分自身の性格や傾向を理解すること)は、支援の質を高める重要な手段です。
自己理解に基づく行動は、利用者の尊厳保持や安心感の提供に直結します。
自分を知ることで、ストレス管理や行動改善も可能になり、日々の業務がより充実したものになります。
1. 自己覚知の重要性
自己覚知とは、自分の性格や感情の傾向を理解することです。これにより以下のメリットがあります:
- バーンアウト予防:自分のストレス傾向を把握して無理のない働き方ができる
- 支援の精度向上:得意・不得意を理解し、行動を調整することで利用者への対応を改善
具体的に活かす方法:
- 日記やチェックリストで日々の感情・行動を記録する
- 自分の強み・弱みをチームで共有し、業務偏りを防ぐ
2. 利用者の個人因子の把握と自立支援の両立
ICF(国際生活機能分類)では、性格や価値観、人生観、生活習慣などが『個人因子』として重視されます。
介護現場では、これらを理解したうえで安全の確保と自立支援の両立を意識することが大切です。
たとえば入浴支援の場面。
利用者が自分でできる動作があっても、安全面への不安がある場合があります。
このとき、必要に応じて声かけや介助で安全を確保しながら、本人が行える動作は性格や能力に応じて段階的に任せることが重要です。
性格特性に応じた支援例:
- 内向的な利用者:観察や丁寧な声かけを通して安心感を与え、少しずつ自分でできる動作を増やす
- 外向的な利用者:積極的な声かけや誘導で、自ら進んで行動できるよう促す
このように、性格特性を踏まえて支援を調整することで、本人の意欲を引き出しながら自立を促すことが可能です。
支援は段階的・計画的に行うことが効果的です。
ABC分析や段階的支援の考え方を活用し、
できることを少しずつ増やす・維持をすることで、
利用者が『介護を受けながら、自律心や自立行動を育むこと』ができます。
段階的支援の実践については
👉『段階的支援の理論背景と実践― しょーくんのケースから学ぶ、科学的に裏付けられた支援の考え方(家族向け)』
で詳しく解説しています。
段階的支援の必要性については
👉『急な行動変容はリスク ― 段階的支援の科学的指導』
で詳しく解説しています。
ABC分析の実践については、
👉『こだわりとは、わがままなのか?──椅子へのこだわりから考える支援の正しい視点』
で詳しく解説しています。
利用者の個人因子を理解し、安全を確保しつつ本人の能力や意欲に応じて自立を引き出す支援こそが、尊厳ある介護の本質です。
この観点を意識することで、日々の支援がより本人中心で、充実したものになります。
3. 自己覚知と自己研鑽
介護現場で質の高い支援を行うには、職員自身の性格や感情傾向を理解すること(自己覚知)が重要です。
これにより日々の行動を振り返り、改善点を見つけることが可能になります。
また、自己研鑽として継続的に学びや工夫を取り入れることで、支援の精度や利用者への対応力が向上します。
具体的な方法例:
- エゴグラム等の性格診断をつかう
- 自分の強み・弱みを整理し、業務で活かす
- 日々の感情・行動を記録
- チームで情報共有し、業務偏りやストレスを減らす
- 定期的に研修や学習で新しい支援方法を取り入れる
これは利用者にも支援者にも言える事ですが、
性格とは固定されたものではなく、自身の成長や置かれている環境と共に変わってきます。
その時の自分や他者の性格(傾向)を把握し理解することは重要です。
4. 具体的なチェックリスト
日々の振り返りに活用できます:
- 今日、自分のストレスや感情を把握できているか
- 利用者の希望や価値観に沿った対応ができたか
- 困った時に相談できる環境を活用したか
- 自己覚知を基に行動修正ができたか
まとめ
自己覚知、個人因子の理解、自己研鑽を組み合わせることで、
介護は『利用者本位で、自分に無理のない支援』
に変わります。
性格特性はラベルではなく、尊厳ある支援を実現するために必要な情報です。
日々の業務の中で、自分の強みを活かし、弱みを補う工夫をすることが、
利用者にとっても自分自身にとっても最良のケアにつながります。
介護現場で働く全ての人にとって、自己覚知は欠かせないスキルであり、尊厳ある支援の基盤です。
介護は給料面では魅力的とは言えませんが、
自己覚知や自己研鑽を通じて他者に貢献できるのが、
この仕事の面白さであり誇りでもあります。
これからも一緒に頑張っていきましょう。
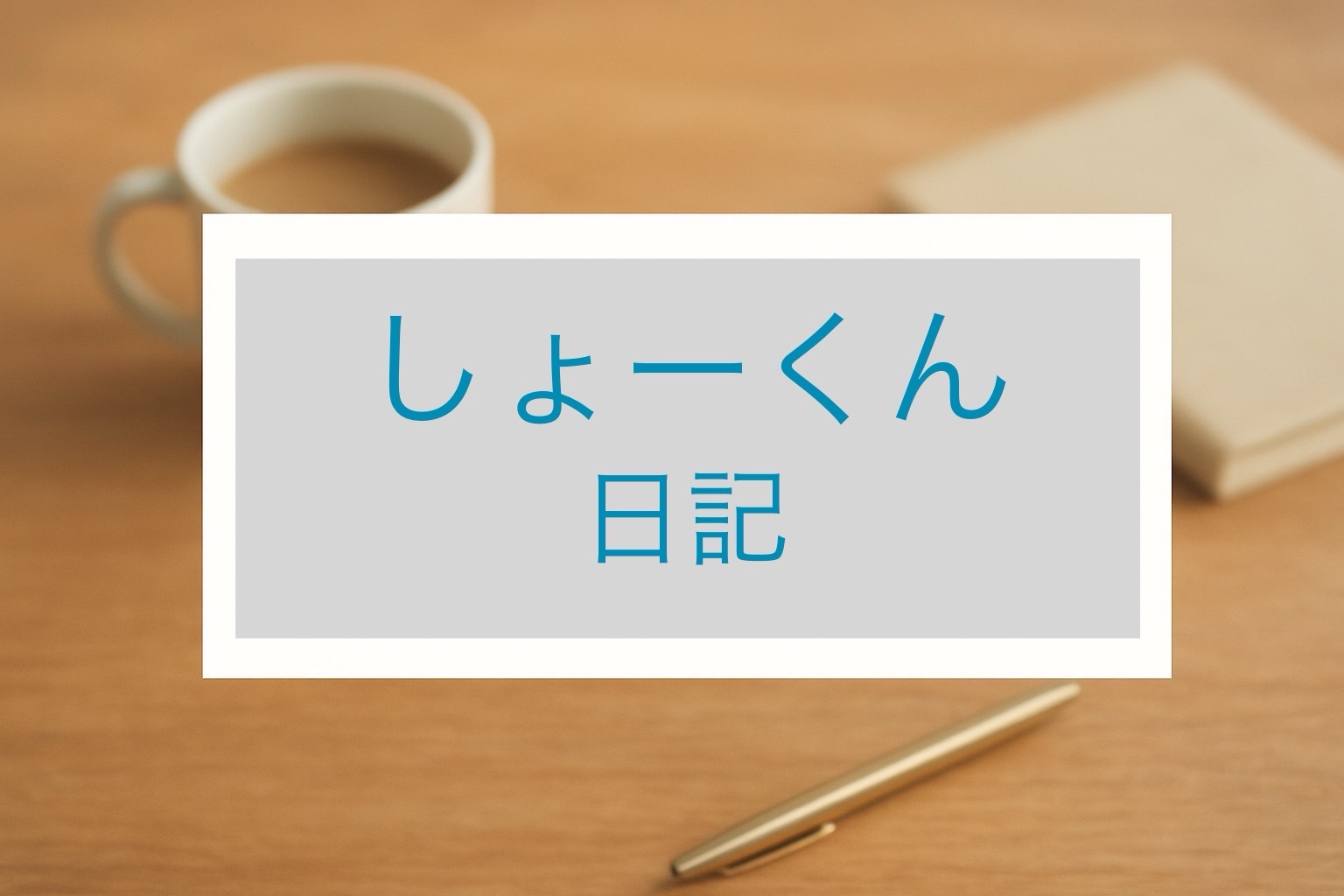


コメント