【第5章】制度は誰のためにあるのか
福祉制度は今、大きな転換期にある。
「就労系障害福祉サービスの在り方」
「就労継続支援B型の長期利用者の多さ」
「生産性の低さ」
「移行実績の乏しさ」
が繰り返し示されていた。
それに続く形で、就労選択支援は、令和7年10月に新設されます。
これは、利用者が適性に合わないサービスに長期間滞留し、成長や就労の機会を失う問題を防ぐために、本人の能力や希望を的確に評価し、最適な支援先を選ぶ仕組みを目指しています。
この流れは「可能性を信じる支援」
「事業所の運営都合による利用者の囲い込みの排除」
として歓迎されるべきである。
しかし、同時に私は問いたい。
「移行できない人」のことは、誰が制度の中で守るのか?
福祉とは、能力主義のフィルターで選別されるものではないはずだ。
私の弟のように、作業はできるが環境調整が必要な人間、
成長はしているが“目に見える成果”としては評価されない人もいる。
B型は、就労福祉サービスの中でも「支援の色が最も濃い場所」として位置づけられてきた。
しかし今、その“色”が制度の中で薄められようとしているように感じる。
制度は“成長”だけではなく“包摂”も起点に再構築すべき
人は誰でも、成長のペースが異なる。
それを
「何年たっても移行しないのは支援が不十分」
「本人の能力が不十分」
とするのは、制度の論理で人間のリズムを切り捨てることにならないか。
制度設計の基本は、できる人に合わせるのではなく、できない人を起点に考えることだ。
例えば、「学校」はそうあるべき場所だ。
クラスの中で勉強が苦手な子がいれば、その子にもわかるように説明する。
わからないからといって教室から排除はしない。
それなのに、「就労」や「支援」の現場になると、急に“能力のある人優先”になる。
- 「より生産性が高い人に、より多くの支援を」
- 「移行できない人に、支援をかけ続けるのは非効率」
そうした空気の中で、「能力の低い人=不要な存在」と見なされかねない。
そんな方向に制度が進んでいないだろうか。
就労系サービスは、働く力を高めるだけでなく、「社会とのつながりを持ち続ける場」としても機能している。
就労継続支援B型は、その中でも最も「支援寄り」であり、
最も「排除されがちな人を包み込む」役割を果たしてきた。
その役割が、制度の論理によって削られていくのであれば、それはまさに“支援の逆行”である。
【制度への提言】多様な就労観に立脚した再設計を
ここで、私なりに「制度が向かうべき方向性」として、以下の点を提言したい。
① 「成長支援」と「維持支援」の明確な分離と両立、及び新設事業所の受け入れ
今の制度は、「成長(移行)支援」が主軸で、
「現状維持支援」は“消極的なもの”として位置づけられているように見える。
しかし、高齢者介護の分野では「維持する支援」は基本とされている。
障害福祉の現場でも、「今の生活を安定して継続する」ための支援を、もっと積極的に制度化すべきだ。
維持支援は、消極的ではなく、非常に前向きな支援である。
また、多様な運営方針を持つ事業所が競争し、福祉理念を守れない事業所は淘汰されるべきだ。
②就労継続支援B型における多機能型運営の柔軟性向上
今後、A型やB型、就労選択支援など、サービス体系が多様化していく中で、「多機能型事業所(複数サービスの併設)」の柔軟な認可・運営を支援すべきである。
同一の事業所の中で、本人の状態に応じて段階的に支援を切り替えられる仕組みがあれば、「急な移行」や「無理な一般就労」が避けられる。
本人にとっても、家族にとっても、より穏やかな変化が可能になる。
③ 地域資源としての就労継続支援B型の再評価
就労継続支援B型は単なる「移行前ステップ」ではなく、地域生活の中で自立を支えている。
地域の高齢者施設や保育園、地元企業との連携を強め、社会参加の拠点となる仕組みを強化していくこと。
これは、地域全体の包摂力を高めることにもつながる。
④ 利用者・家族が制度設計に参加できる場の創出
現行の制度設計に当事者や家族の声が十分反映されていない問題を解消し、
安心して意見を言える環境を整えることが必要です。
不利益を恐れず意見を伝えられる仕組みや、政策に反映されるルートの確立を求めます。
【さいごに】「役に立たない」人など、いない
弟は、社会的な意味での“生産性”は高くないかもしれない。
けれど、彼は確実に「自分のペースで社会とつながり、誰かの役に立ちたい」と願っている。
就労継続支援B型は、そんな願いを受け止めるための場所であるべきだ。
それを“過渡期のサービス”として制度から切り離すのではなく、
すべての人が社会と関わり続けるための基盤として、
正当に評価し、継続的に支援すべきだ。
「役に立たない人間」はいない。
ただ、社会の側が「どう受け止めるか」で、意味は変わる。
その受け止め方を決めるのが、「制度」だ。
福祉制度が、すべての人にとって「居場所と誇り」を保障するものとなるように。
私は、家族として、これからも問い続ける。
🔽 ご意見・ご感想をお待ちしています。
ご覧いただき、ありがとうございました。
制度設計に関心を持っていただけた方、どうか現場の声を拾い上げてください。
次回
障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編)
次回の記事へ
しょーくんと私の仁義なき戦いは
こちら
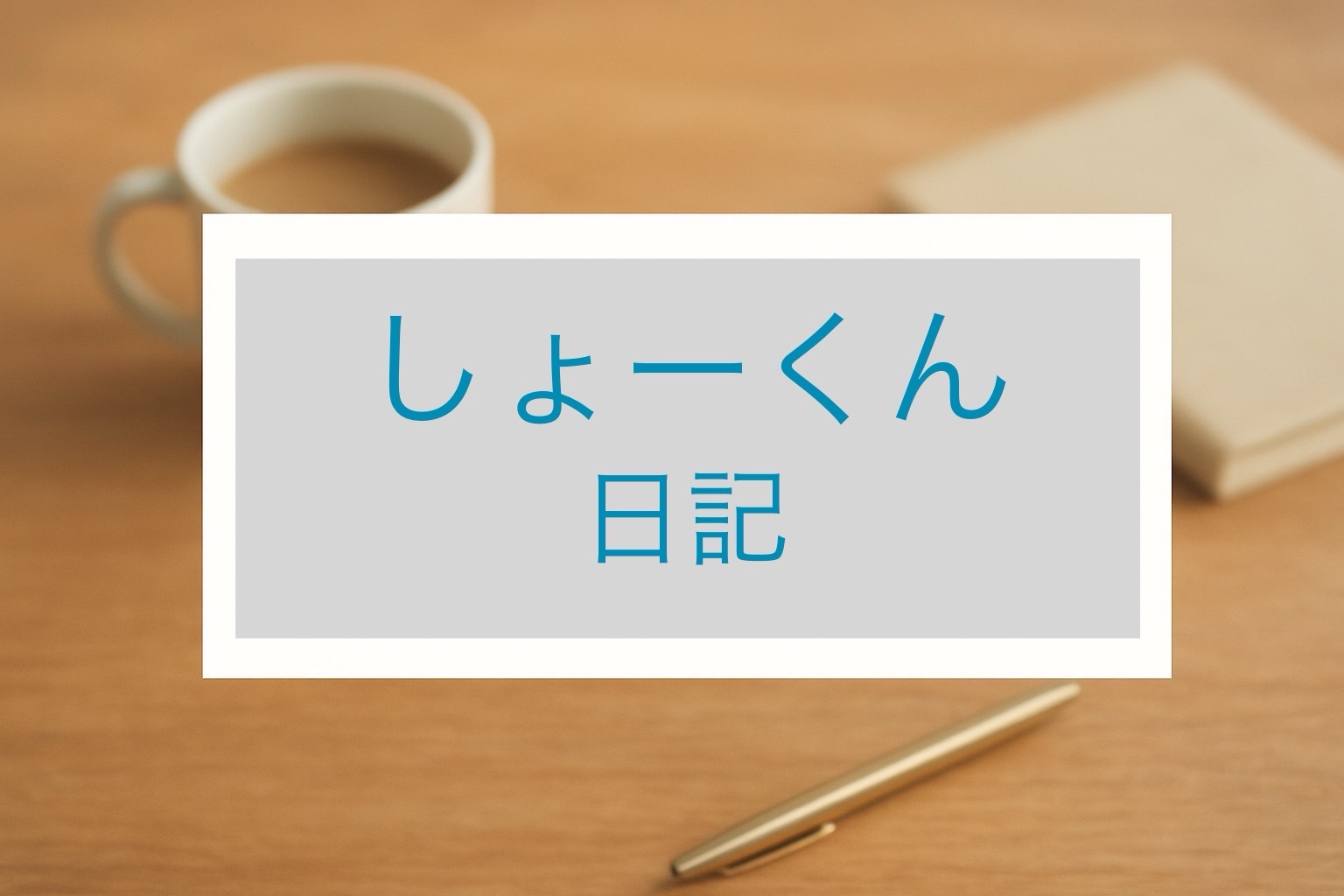

コメント