本ページはプロモーションが含まれています。
1. 副業を始める決意と現状
売り上げは少なく、行政からの報酬も下げられ、資金繰りは日々厳しい。
しかし、諦めるわけにはいかない。福祉に関わる人々の声が、胸を強く打つからだ。
「あーちゃん、障害者のグループホームを作って欲しい!」
補助金を調べてみよう。建物を先に建てなければならないのか
――財布の中身を覗き込み、そっと閉じる。
稼ごう。何か稼がなければ、この状況は変えられない。
福祉は社会に軽んじられ、政治も声を無視する。
私はこの腐った状況を、行動を通して変えていきたい。
自分の将来は誰が助けてくれるだろう……?
誰も助けてはくれない、自分がやるしかない。
それは今も昔も変わらない。
資金確保の手段として、投資やNISAも検討しよう。
投資、儲かるのだろうか・・・
――儲けがなければ、事業も進まない。
現実を変えるためには、まず自分の資源、主に現金が必要だ。
ネットで目にする声も、わたしを後押しする。
現実は、まさに副業大航海時代だ。だから、まず行動だ。
2. 副業テーマの決定:福祉・ブログ・アフィリエイト
福祉のためなら手段を選ばない
――そう自分に言い聞かせる。
副業を検索してみる。「アフィリエイト」「ブログ収入」
――とりあえず、この二つを軸にしてみよう。
ブログにどんなことを書くか調べていると、「スキルを提供する」というフレーズが目に入った。
「(スキルを提供する……?)」
よくわからないが、その通りに動いてみることにした。
渇望と怒りをエネルギーに変えて、事業や副業に活かすのだ。
ブログを書く中で、副業としての取り組みだったはずが、気づけば本業の延長として福祉に向き合うことになっていた。
幸い、カフェ運営時に定款を改め、さまざまな事業に対応できるようにしてある。
3.自分の財産とスキルの棚卸し
私の人生で何が財産になっているのか。
私が提供できるスキルは何か。
ふと考える。何か役に立つことはあるだろうか?
まずは介護過程を書き出してみることにした。
(詳しくは『介護過程(前編1)』、『介護過程全体像まとめ』の記事へ)。
これまでの歩みを振り返ると、訪問介護の立ち上げや運営経験、カフェ事業での学びなどが、自分の大きな財産であることに気づく(詳しくは
①『高校生の私が描いた夢――弟と家族を守るための福祉起業ストーリー』、
②『副業や小さな事業で失敗しないコツ!契約書とルールで人間関係トラブルを防ぐ事例』
の記事へ)。
これまでの経験や知識を整理することで、今後の事業や副業にどのように活かせるかを明確にしたい。自分の渇望や怒りも、行動の原動力として前向きに使っていくつもりだ。
4.オススメする副業
ブログやスキル提供の過程で、私はあることに気づいた。
福祉として届けたいのは、利用者やその家族だけでなく、日々汗を流す働き手
――担い手にも報われてほしいという思いだ。
※参考:副業に関しては、私はいくつかのサイトや動画を参考にして学びました。自分の経験と照らし合わせながら、実践できそうな方法を取り入れています。
ここで、私はあなたにも、まずブログを書くことをオススメする。
なぜなら、自分の経験を整理し、副業としても活かせるからだ。
- 訪問介護等で得た観察スキルは、記事のテーマ整理に活かせる
- 福祉知識をもとに、アフィリエイトで福祉関連情報を紹介できる
- 副業での情報発信は、本業の経験整理にもつながる
こうしてアウトプットすることで、スキルを最大限活用できる。
5.副業を通じて芽生えた福祉への思い
社会や政治は福祉の声を軽んじる。
しかし、介護職が副業に興味を持つ、
もしくは副業に関心を持つ層が福祉に関わりをもつ。
そうすれば、新しいサービスを生み出す可能性がある。
具体的には、
- 現在の福祉職が副業に興味を持ち、独立して新しいサービスを作る可能性
- 福祉に興味がなかった層が、副業から福祉事業に携わる可能性
――いずれも、この可能性が実現すれば、社会の福祉資源が増え、助かる人が増える。
さらに1.2.に関わる人々も、活動を通して利益を得ることができる。
そして、この活動(ブログ)から生まれる現金は、
私が目指すグループホームの実現になり、
ブログでの発信による知恵や体験の提供は、
現場で汗を流す担い手を報いるための力となる。
収益は単なる手段ではなく、福祉を支える現実的なリソースだ。
思考は自然と福祉に向かう。
行動を通して、福祉を強く、影響力のあるものに変えていきたい
――この取り組みは、福祉実現への新たな航路であり、同時に現金獲得の現実的手段でもある。
6. 次の一歩に向けて
私は今、文章を書き、経験や思いを整理することから始めている。
この整理が、次の行動の地図になる。
- 短期(1~12か月)
まずは自分のスキルや知識を整理し、ブログ記事や資料として発信する。目の前で確実にできることを積み重ねることで、行動の実感を得るのだ。 - 中期(1年~3年)
副業をしたい層に情報提供し、福祉に関心を持つ層を増やす。
彼らは新しいサービスを生み出す可能性がある。
私はグループホームの設立の費用を集める事を目指しつつ、
福祉であるか・ないかに関わらず、事業を広げる。 - 長期(3年~10年)
少しずつ収益を増やすことで、グループホームを実現させる。
その道中で、自分も新しい福祉に関わるサービスの創設を検討する。
現金や人材は、単なる手段ではなく、福祉を支える現実的なリソースだ。
焦らず、現実の手応えを積み重ねて夢に近づける。
短期は手堅く、中期は可能性を探り、長期は夢を現実に近づける
――この三段階で、私の航海は進む。
渇望と怒り、社会を変えたい思いを胸に、今日も一歩を踏み出す。
福祉実現への航海は、まだ始まったばかりだ。
あなたの経験や知識も、福祉の力になるかもしれません。
まずは小さな一歩を踏み出してみませんか?
関連記事:
- 夢の始まりと葛藤を描いた実話については、
👉『高校生の私が描いた夢――弟と家族を守るための福祉起業ストーリー』
をご覧ください。 - 契約やルール作りの実践例については、
👉『副業・小さな事業で失敗しない!契約書とルールで人間関係トラブルを防ぐ方法』
で詳しく解説しています。 - 業務整理と職場改善のヒントについては、
👉『【実務で使える】業務の洗い出し・棚卸しと職場環境改善計画の作り方(前編)』
で実態を解説しています。
- 訪問介護制度の“抜け落ち”については、
👉『「家庭で支える前提」の訪問介護制度が、担い手を限界に追い込んでいる【前編】──現場から見た制度の“抜け落ち”と提案』で詳しく整理しています。 - 就労支援B型の未来と不安については、
👉『就労継続支援B型の未来に、不安と願いを込めて【前編】
──弟の働く場所が、制度の中で削られていくかもしれない』
で詳しく解説しています。
- 介護過程はPDCAを使います。介護過程の基礎と応用は、
👉『障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編1)』
で詳しく解説しています。
👉まとめ版はこちら『障害児家族にもオススメする介護過程(全体像まとめ)』 - 自閉症児の『こだわり』への支援については、
👉『こだわりとは、わがままなのか?──椅子へのこだわりから考える支援の正しい視点』
で詳しく解説しています。 - 科学的に裏付けられた支援については、
👉『段階的支援の理論背景と実践― しょーくんのケースから学ぶ、科学的に裏付けられた支援の考え方(家族向け)』
で詳しく解説しています。 - 発達障害児への段階的支援の必要性については
👉『急な行動変容はリスク ― 段階的支援の科学的指導』
で詳しく解説しています。
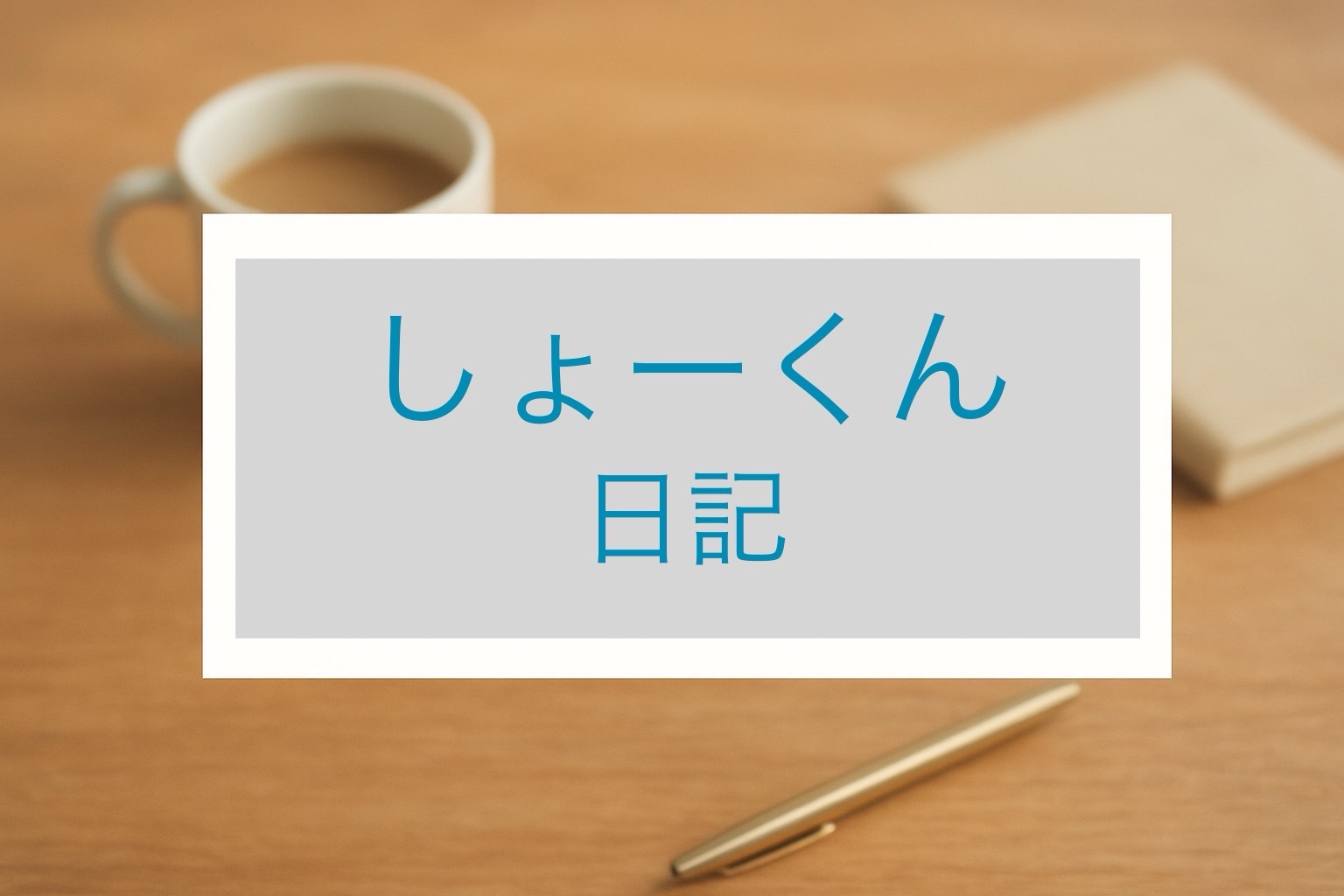


コメント