高校生の私の不安と家族への思い
高校2年生の頃、進路に迷う一方で、弟や祖父母、将来の親の介護に不安を感じていました。
「もし自分が仕事をしている間に何か起きたら、私はちゃんと対応できるのだろうか」と不安で胸がいっぱいになる日々でした。
家族の中でとくに大きな影響を受けたのは、弟の存在でした。生活に支援が必要な弟を支える中で、「きょうだい児」としての葛藤や責任を強く感じてきました。
障害者支援の未来と不安については、
👉『就労継続支援B型の未来に、不安と願いを込めて【前編】
──弟の働く場所が、制度の中で削られていくかもしれない』
で詳しく解説しています。
業界で感じたギャップ――真のプロはいなかった
当時、現場を見て強く感じたことがあります。それは、「この業界にはまだ、真のプロはいない」ということでした。
暴れる弟を前に、多くの支援者はその場をすぐに離れました。中には二度と家に来てくれない人もいました。
ある日、運営者が泣きながら『もう私たちには対応できません…すみません…』と頭を下げたこともあったそうです。
その話を聞いた瞬間、なんだか胸がぎゅっと締めつけられるような感覚に襲われ、介護現場の厳しさを肌で感じました。そして、「誰もやれないなら、この仕事は自分がやるしかないかもしれない」と、直感的に思いました。
当時は、強度行動障害支援者養成研修もなく、福祉制度や研修では十分な対応が整っていませんでした。
それでも私は筋力に自信があり、恐怖を感じずに弟を受け止めることができました。暴れる原因を探る過程で、他の介護関係者にはできないことを自分ができると気づきました。
「あぁ、これは自分に向いている仕事なんだろうな」と確信しました。
障害者への具体的な支援について
自閉症児のこだわりに対しての支援は
👉『こだわりとは、わがままなのか?
──椅子へのこだわりから考える支援の正しい視点』
で詳しく解説しています。
発達障害児への支援は
👉『段階的支援の理論背景と実践― しょーくんのケースから学ぶ、科学的に裏付けられた支援の考え方(家族向け)』
で詳しく解説しています。
発達障害児への段階的支援の必要性については
👉『急な行動変容はリスク ― 段階的支援の科学的指導』
で詳しく解説しています。
ヒントをもらった体験――自宅での訪問介護経営者の姿
母と一緒に、外国人の訪問介護経営者が自宅で事業を運営する様子を見ました。
「自宅でもできるのか」と感じ、自分で事業を運営すれば、弟のお気に入りのヘルパーさんにたくさんお給料を払える体制も作れるかもしれない、と希望が湧きました。
弟もヘルパーさんも守れる――そう思えた瞬間でした。
「この人のマネをすれば、弟の日常生活や大切な支援者を自分で守れるかもしれない」と、今後の人生への希望がみえました。
こうした体験と進路への迷いが重なり、「福祉と仕事を両立するにはどうすればいいか」という問いが、私の副業や事業のアイデアにつながっていきました。
下積みの10年間――経験と葛藤の蓄積
①施設での経験
いきなり訪問介護で自分一人で訪問するのは、対応できるか不安でした。
だから最初は介護技術を学びたいと思い、施設で働きました。
業務に追われ、誰が誰かわからないまま一日が過ぎる感覚に、不安と焦りが重なりました。
看護師に囲まれて詰められたり、財布を落としただけで注意されたり……施設は正直怖く、
「これが自分の働きたい場所なのか」と疑問を抱えながらも、必死に日々をこなしました。
②訪問介護の経験
もっと幅広く支えたい
19歳になる前の1年間、親も訪問介護員の経験があったので、「介護の現場でどんなことをできるようになればいいか」と聞きました。
その中で、親から調理を学ぶことになりました。
「どんなものを作るの?何を作れるようになれば応用が効く?」と尋ねると、親は「煮物かな。肉じゃがが作れたら応用がきく」とアドバイスしてくれました。
初めての料理に挑戦する毎日は、介護現場で役立つスキルを身につけるだけでなく、
自分に少しずつ自信を与えてくれる時間でもありました。
その後、訪問介護の現場に移りました。
学生の頃から福祉の現場に関わってきましたが、やはり印象に残っているのは 訪問介護 の仕事でした。利用者さんの自宅に伺うと、その人の暮らしそのものに触れることになり、施設とはまったく違う学びがあります。
訪問介護の制度や現場の課題については、
👉『「家庭で支える前提」の訪問介護制度が、担い手を限界に追い込んでいる【前編】──現場から見た制度の“抜け落ち”と提案』
で詳しく整理しています。
固定化された利用者を何度も訪問するうちに、高齢者だけでなく、もっと幅広く支えたいという思いが強まり、もどかしさが募っていきました。
③専門学校での学び
知識や技術が足りないことを痛感し、一旦社会人を辞め専門学校へ。
介護の論理や介護過程を体系的に学び、理論と現場経験をつなげる力を身につけました。
ここで初めて、訪問介護にも利用者ごとの計画(ケアプラン)が存在することを知り、
支援の根拠や方向性を体系的に理解できるようになりました。
指示されることだけをこなしていた虚しさが晴れる感覚に胸が軽くなり、
学ぶことの楽しさと、自分の成長を実感できる喜びが湧きました。
専門学校で学んだ計画書の書き方について
介護過程については
👉『障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編1)』
で詳しく解説しています。
👉長いので、『まとめ』ておきますね。
④事務兼訪問介護での経験
事業の内部での動きをみたくて、専門学校卒業後は事務兼訪問介護として働きました。
現場のリアルと制度・書類の仕組み、さらに事業の内部での動きを同時に理解する日々。
給料は変わりませんでしたが、サービス提供責任者に任命され、主に計画書を作成することになりました。
自分の判断で支援計画を組み立てられる楽しさに、仕事の充実感を強く感じました。
事業所運営については、
👉『【実務で使える】業務の洗い出し・棚卸しと職場環境改善計画の作り方(前編)』
で実態を解説しています。
下積み期間中の葛藤
当時の私は、3つの選択肢で揺れていました。
ひとつは、訪問介護で独立して自分の事業を持つこと――心が最も惹かれた道です。
もうひとつはケアマネジャーを目指すこと。
調べてみると、経験年数は勤務時間ではなく「日数」でカウントされると知り、
「パートからでも目指せるんだ!」と現実味がありました。
最後は、入所施設を持つ会社に雇われて働くこと。
もし自分の家族をそこで見られるなら、仕事を休む負担が少なくなるかもしれないと考えたのです。
実際どれを選ぶのか。
そして、この3つの選択肢を選ぶまでにどうするのか。
過去を振り返り考えていました。
施設での忙しさや対人関係の劣悪さ、訪問介護での成長実感の薄さ、専門学校で学んだ制度や理論、
事務兼訪問介護で知った事業の内部事情――こうした経験が重なり、私は進路に迷いながらも、
最も自分の心が惹かれる道を探していました。
- 独立してケアマネジャーになる道
- 独立して訪問介護事業所を運営する道
- 施設がある職場で雇われとして働きながら、自分の家族を支えていく道
それぞれにメリットと不安があり、決断は簡単ではありませんでした。
偶然のチャンス――転機となった予期せぬ出来事
専門学校卒業後、事務兼訪問介護として働いていた私は、
ブラック体質の社風に合わず体調を崩してしまいました。
休日にも「〇〇に参加しないなら代わりを探してこい!日曜でも関係ない!タイムカードは打つな!」
などと言われ、あまりのストレスで難聴になってしまったのです。
結局、仕事を辞めることにしました。
親には「死ななけりゃなんでもいい。お願いだから生きてて」と言われました。
その言葉に甘えて、その後の一年間は、耳鼻科に通いながら
位置情報ゲームで気分転換をしたり、のんびりとニート生活を送りました。
しかし、このままではまずいと思い、友だちの紹介でレジ打ちのアルバイトを始めました。
すると、思いがけない連絡が入りました。
ある日、外国人経営者から「電話番を手伝ってくれないか」と声がかかります。
最初は本当に“電話を取るだけ”の簡単な仕事のはずでした。
ところが、現場に入ると状況は一変しました。
請求業務や各種対応、問い合わせの処理……気づけば、事業所の業務をほぼ一人で回すことになっていました。
初めての経験で緊張が続きました。
「失敗したらどうしよう」「利用者に迷惑をかけたら」と、不安も頭をよぎります。
それでも、下積みで培った知識や経験、現場対応力が少しずつ力を発揮し、前に進むことができました。
1か月間、事業所をひとりで動かした経験は、私に**「独立してもやれる」という確信**を与えました。
偶然のチャンスが、私に覚悟と自信を刻み込んだ瞬間です。
独立への第一歩――法人設立と初めての行動
どの道も本気で考えましたが、縁もあって、私は訪問介護で独立する道を選びました。
あんなに悩んでいたのに、きっかけさえあれば、独立の準備は思ったよりも速かったものです。
独立にあたり、最初の壁は「法人設立」でした。
1. 法人設立
法人を立ち上げるには、定款の作成や登記などの手続きを踏む必要があります。
特に「定款の作成」は最初の大きなステップで、
雛形や手順は
👉『法務局の公式サイト』
でも確認できます。
私もこの手続きには戸惑いましたが、公式情報を見ながら進めることで、不安を減らすことができました。
2. 制度を使った事業を始めるための申請
法人を設立しただけでは、介護事業や障害者支援サービスを制度として利用することはできません。
事業を開始するには、法人として市町村に申請を行う必要があります。
このとき、法人の定款には 該当する法律名の記載 が必要です。
もし法律名が記載されていなければ、申請は受理されず、制度を利用した事業はできません。
さらに、訪問介護などのサービスを行う場合は、各事業ごとに申請書を市役所や県庁に提出します。
書式は各市町村のホームページからダウンロードできますが、どのページのどの書式を取得すればいいかは、初めての方にはわかりづらく、ハードルが高い作業です。
そのため、制度を使って介護や障害支援を始める場合は、まず最寄りの市町村に相談することをおすすめします。
3.介護の請求ソフト
介護の請求ソフトは、いろいろ検討しました。
①初期導入費を抑えるために、私は
👉『国保中央会介護伝送ソフト』
を購入しました。
60,000円(消費税・送料込)です。
外国人経営者も同じ物を使っていました。
※買い切りタイプですが、3年か4年に一度買い替えが必要です。
あと電子請求登録料も3.4年に一度更新が必要です。
詳しくは直接連絡してください。
はっきり覚えていなくてすみません。
ただ、個別計画書やシフト・予定表・業務日誌・
タイムカードなどは入っていません。
請求ソフトのみのタイプになります。
でも、請求ソフト以外って実は自作できるんですよね。
私も前の会社も、外国人経営者も、自作物で指導を通過しています。
これは自作できる方向けですね。該当事項を抜けなく作れる人向け。
これ一つで、介護と障害、両制度の請求ができるのは大きいですよね。
例えば訪問介護と居宅介護(障害者宅への訪問介護)が、
(6万円+α)÷3年=
月に1,666円+(α/3)で出来る感じです。
月2,000円ほどはかなり安い。
私は国保中央会介護伝送ソフトを使っているので、
実際には使ったことがないけど
②介護の請求ソフトや個別計画書が無い方は、
👉『介護ソフト「カイポケ」』
などがオススメだと思います。
国保中央会介護伝送ソフト以外だと、
一番よく聞く名前ですね。
レセプト・記録機能・帳票作成がついて
月に25,000円です。
一桁変わっちゃうけど便利なんでしょうね。
4.就業規則
処遇改善加算を取るためには就業規則が必要でした。
それだけではなく、実際にこの就業規則が機能して助かったことがあります。
次回の
👉『副業・小さな事業で失敗しない!契約書とルールで人間関係トラブルを防ぐ方法』
で詳しく解説しています。
モデル就業規則は
👉『厚生労働省の公式サイト』
でも確認できます。
届け出や書類作成、行政とのやり取り、人員基準の確認……すべてが初めてのことで、手探りの連続。
しかし、下積みの10年間で培った現場での対応力や柔軟性、そして事務スキルが、
この壁を乗り越える大きな力となったのです。
最初の利用者を迎えた日
法人が設立され、ついに最初の利用者を迎えました。
自分の事業で利用者の生活を支える責任は重く、
緊張とプレッシャー、同時に少しの不安もありました。
しかし、施設での経験、訪問介護での学び、専門学校で得た理論、
事務兼訪問介護で知った制度や書類の仕組み――すべてがここで生きました。
利用者と向き合い、支援計画を実践し、日々のケアを調整していく中で、
「自分が理想とする福祉」を少しずつ形にできる手応えを感じました。
この体験を通して、十年の下積みが決して無駄ではなかったことを実感しました。
最後に一言
迷いや不安は、誰にでもあります。
自信が持てず立ち止まることもあるでしょう。
でも、それは恥でも失敗でもありません。
経験や小さなチャンスを重ねることで、
少しずつ自分の力の使い方や世界の見え方が変わっていきます。
不安は完全には消えなくても、まず一歩を踏み出すことで進める感覚をつかめます。
だから、怖がらずに今日できる小さな行動から始めてみてください。
その一歩が、思わぬ学びや出会いにつながり、
自分や家族、周りの未来を少しずつ変えていきます。
迷いや不安を抱えながらでも、行動した瞬間から、あなたはすでに未来を切り拓き始めています。
――その一歩が、まだ見ぬ未来を開く、あなた自身の「最初の瞬間」になる。
まずは、小さな一歩から始めてみませんか?
今日できそうなことをひとつ選んで、気軽に踏み出してみましょう。
次回は
👉契約やルールの作り方、失敗しない小さな挑戦の実践例
です。
まとめリンク集
障害者支援の未来と不安については、
👉『就労継続支援B型の未来に、不安と願いを込めて【前編】
──弟の働く場所が、制度の中で削られていくかもしれない』
で詳しく解説しています。
障害者への具体的な支援について
自閉症児のこだわりに対しての支援は
👉『こだわりとは、わがままなのか?
──椅子へのこだわりから考える支援の正しい視点』
で詳しく解説しています。
発達障害児への支援は
👉『段階的支援の理論背景と実践― しょーくんのケースから学ぶ、科学的に裏付けられた支援の考え方(家族向け)』
で詳しく解説しています。
発達障害児への段階的支援の必要性については
👉『急な行動変容はリスク ― 段階的支援の科学的指導』
で詳しく解説しています。
訪問介護の制度や現場の課題については、
👉『「家庭で支える前提」の訪問介護制度が、担い手を限界に追い込んでいる【前編】──現場から見た制度の“抜け落ち”と提案』
で詳しく整理しています。
専門学校で学んだ計画書の書き方について
介護過程については
👉『障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編1)』
で詳しく解説しています。
👉長いので、『まとめ』ておきますね。
事業所運営については、
👉『【実務で使える】業務の洗い出し・棚卸しと職場環境改善計画の作り方(前編)』
で実態を解説しています。
法人を立ち上げるには、
定款の作成や登記などの手続きを踏む必要があります。
雛形や手順は
👉『法務局の公式サイト』
でも確認できます。
介護の請求ソフトは、いろいろ検討しました。
①初期導入費を抑えるために、私は
👉『国保中央会介護伝送ソフト』
を購入しました。
60,000円(消費税・送料込)です。
外国人経営者も同じ物を使っていました。
6万円+α÷3年=
月に1,666円+(α/3)で出来る感じです。
月2,000円ほどはかなり安い。
介護の請求ソフトや個別計画書が無い方は、
👉『介護ソフト「カイポケ」』
などがオススメだと思います。
国保中央会介護伝送ソフト以外だと、
一番よく聞く名前ですね。
月に25,000円です。
処遇改善加算を取るためには就業規則が必要でした。
それだけではなく、実際にこの就業規則が機能して助かったことがあります。
契約やルールの作り方、失敗しない小さな挑戦の実践例
👉『副業・小さな事業で失敗しない!契約書とルールで人間関係トラブルを防ぐ方法』
に詳しく解説しています。
モデル就業規則は
👉『厚生労働省の公式サイト』
でも確認できます。
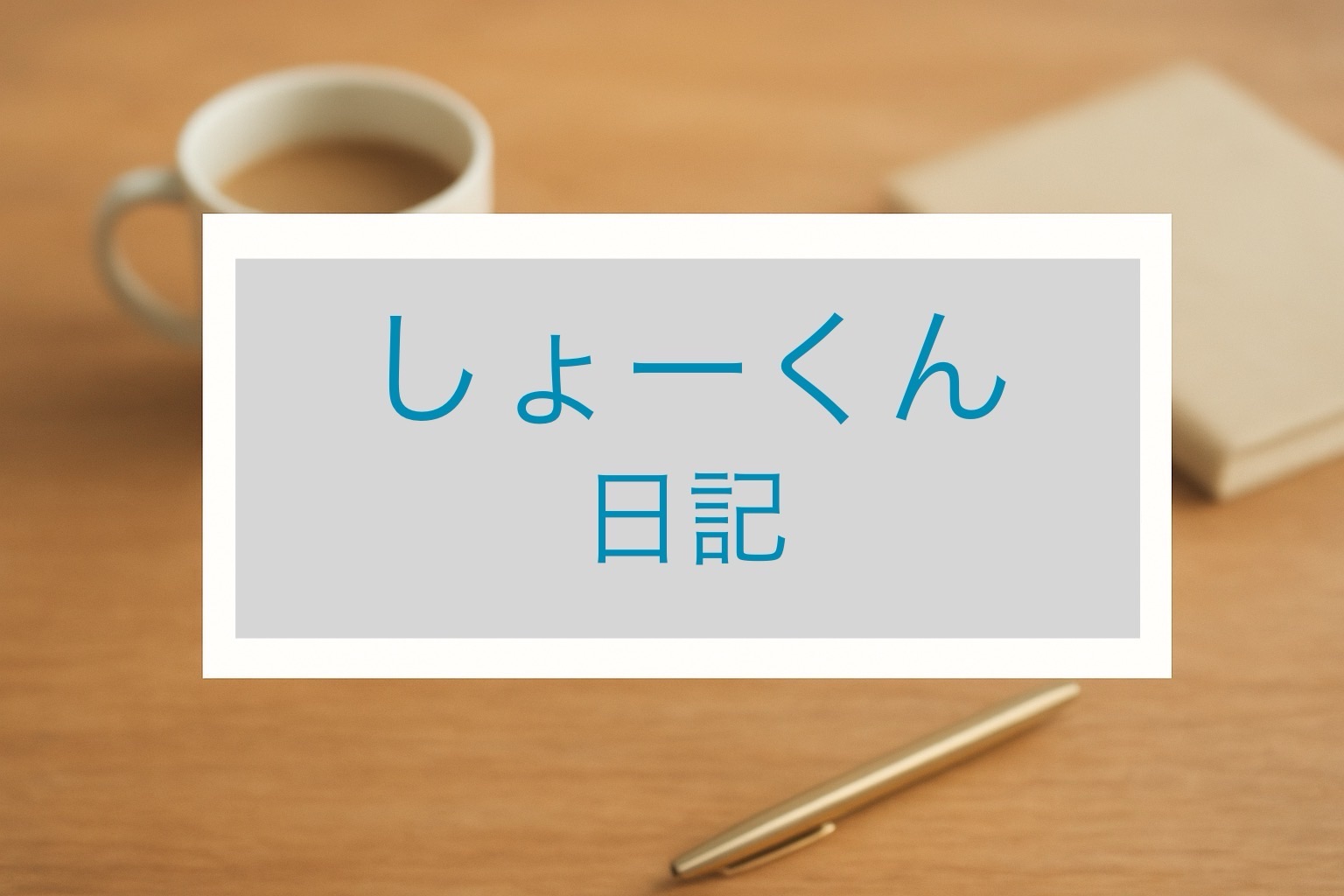


コメント