きょうだい児として育ってきた私が感じた悩みや葛藤を書きます。今まさに悩んでいる人や、これからを不安に思っている人の参考や希望になれば嬉しいです。
- 障害のある家族について悩んでいる(現在についての不満)
- 介護者の老化に伴う不安(未来への不安)
そんな誰かの為に、自分の経験が役に立てればと思いこの記事を書きました。
1.30年ほど前、私はきょうだい児になった
今から30年ほど前、私は2歳できょうだい児となりました。当時、児童デイサービスはなく学校や保育園の送迎から帰宅後の対応まで、すべて家族が支援していました。
現在の日本では障害児が生まれても居宅介護、移動支援、児童デイサービス等があり、障害児の療育環境は整いつつあります。
しかしすべて行政機関でまかなえているわけではなく、今も昔も変わらず家族にしか分からない苦労はあります。
私の年表
- 普通の子供としての人生は2年(2歳)
- 片親になったのが5歳の頃
- ヤングケアラーとしての年月は18年ほど(私:20歳ぐらい)
- しょーくん(弟)が徘徊や逃走、破壊行動、他傷・自傷行為がなくなった年齢(18歳ぐらい)
2.きょうだい児・者になって直面した3つの悩み
家族の中でとくに大きな影響を受けたのは、弟の存在でした。
生活に支援が必要な弟を支える中で、私は「きょうだい児」としての葛藤や責任を強く感じてきました。
私が学生の間は色々な出来事に対し感情の振れ幅が大きく、精神的に休まりませんでした。
まずは自分がきょうだい児だったころを振り返ります。
2-1.悩み①:障害のあるきょうだいに振り回される日常
きょうだい児として育つと、自分の生活が親や障害のあるきょうだいに振り回されることがあります。
疲弊度合いが強いため、きょうだい児によっては自分を守るために距離を置くことも珍しくありません。私の経験を振り返ってみます。
私は高校生活を楽しんでいました。
当時、弟のしょーくんは15歳前後で、ほとんど発語がありませんでした。
意思を伝えられないストレスからか、自傷行為や窓ガラスを壊すこともありました。今振り返ると「よくあんな状態で家にいたな」と思います。
ある日、しょーくんの学校が休みで、母もパートを休んでいました。私だけが登校する日です。
授業中、担任の先生に呼び出されました。
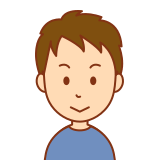
弟さんが暴れているので、家に帰ってきてほしいとお母さんから連絡がありました。どうしますか?
私は心の中で迷いました。

(今日は母と弟だけの家で心配。でも授業中だし嫌だな…)
(でも連絡が来たのは、たぶん大丈夫じゃないからだよね…)
(高校に来た努力が無駄にならないかな。不安だ…)
結局、私は

わかりました。帰ります。
と答え、自転車で家に戻りました。
しかし、家に着くとしょーくんは落ち着いていました。
安堵と同時に怒りが湧いてきます。

今は大丈夫やん!なんで呼んだんや…
母にその気持ちをぶつけました。母は謝ってくれました。
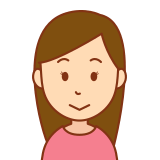
ごめんね、学校頑張ってるのに頼っちゃって…
私も少し納得しましたが、それでも疲れは残っていました。結局、学校には連絡して休むことにしました。
こんなふうに、きょうだい児の生活は情緒も日常もジェットコースターのように揺さぶられます。
誰かが悪いわけではありません。理不尽に感じることも多いのです。
また、親の関心が障害のあるきょうだいに向いていると感じると、心が離れてしまうこともあります。
当時の私は、自分の気持ちにすら気づかず、言葉にすることもできませんでした。
きょうだい児なら、大なり小なり似たような経験をしている可能性が高いです。
2-2.悩み②:親の老後ときょうだいの将来を同時に背負う不安
現実問題として、私はこう感じていました。
『親ときょうだい、自分の今後に思考のリソースが割かれる。』

(これから必ず来る親の老後、親も見なきゃだけど、誰が弟をみていくのか…)
知識もないのに、この年齢で親の介護、きょうだいの介護、自分の将来まで考えなければなりません。
普通なら自分の人生だけを考えればいいはずなのに、「親」「きょうだい」「自分」の三つを同時に考えてしまうのです。
その結果、高校生になるまで私は、将来の夢や目標を持つことができませんでした。

(普通、こんなことを今から考えてる同級生っているんだろうか…)
さらに不安を強めたのは、周囲の言葉でした。
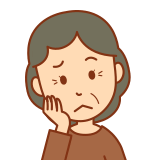
あーちゃん、大きくなってもしょーくんのこと見てあげてね。

おねーちゃんは弟のお世話をするものだ。
あーちゃん、しっかりしてるし、頼んだぞ。
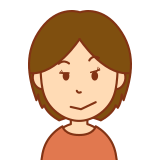
しょーくんを見て、ママを助けてあげてね。
当時の私は、これらの言葉を思わず「呪い」のように感じていました。
でも、母は私を安心させてくれました。
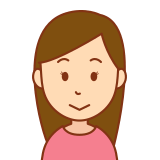
あーちゃん、大丈夫。
もしママがしょーくんを見られなくなったら施設に預ければいい。
時々顔を見に行ったり遊んであげるだけで、ママは満足。
あーちゃんはあーちゃんでいていい。
大人になってから無理に面倒を見る必要はないよ。
母の言葉に、少し心が軽くなったのを覚えています。
とはいえ、一度「自分が見なくてはならない可能性」を意識すると、責任感で押しつぶされそうになります。

(母を一人にするわけにはいかない。
父親はいないし、ただでさえ苦労をかけている母に、
これ以上負担をかけたくない…)

(…でも、学校に行ってる時ですら呼び出しがかかるのに、
私は社会人としてやっていけるのだろうか…)
不安で胸がいっぱいになる日々でした。
2-3.悩み③:きょうだい児に襲う孤独感とプレッシャー
自分の人生だけでなく、将来自分一人で親やきょうだいの世話をしなければならないのでは、というプレッシャーと孤独感があります。

(もし父親がいれば、もっと肩の荷を下ろして子どもらしくいられたのかも…)
いや、でもあの父親じゃ無理だな。悪影響が大きいから、いない方がマシかもしれない。

(もし自分の父親が「良いお父さん」だったら、
きょうだいは両親に任せて、
自分の人生を謳歌できたのかも…
良い父親って、そもそもどんな人か分からんけど…)
結局、私はこう思うしかありませんでした。

(無いものねだりしても仕方ない。
じゃあ、実際私はこれからどうすればいいんだ…)
さらに、結婚や友人関係では、障害のあるきょうだいに関する心理的負担もあります。

(結婚する時も、きょうだいのことを打ち明けるのはシンドイだろうな…
友達を家に呼ぶ時、きょうだいのことを拒絶されないか気になるのに。
結婚の時、義理の家族に受け入れてもらえるかな…
今受け入れられても、将来もし障害のある子を産んだら、
自分のせいにされるかも…)
実際には微妙な反応で終わることが多いのですが、反応に困られるのがしんどいのです。
家に呼ぶのは恥ずかしくないけれど、変なプレッシャーがあって面倒に感じることもあります。
そして、このように、他者に拒絶されるかもしれないという不安と恐怖が常にあり、非常に大きなエネルギーを消耗します。
この孤独感とプレッシャーをはっきりと感じたのは中学生の頃でした。そして、受験や就職など、自分の人生に関わる大きな選択のタイミングで特に強く襲ってきます。

(こんな気持ちになる同級生なんていないよな…
身近で同じ境遇の人がいないから、
誰もこの気持ちを分かってくれない…)
結果として、自分の人生だけでなく、将来自分一人で親やきょうだいの世話をするかもしれないというプレッシャーと孤独感が重なり、常に精神的に消耗しやすくなります。
3.3つの悩みを乗り越えた方法
3-1.明確な人生設計を立てた
自分の人生をどう歩みたいかを具体的に考え、紙に書き出しました。
こうすることで、日々の感情や家族の状況に振り回されても、
ぼんやりでも行き先が見えるようになりました。

(母と弟を守りながら、自分の仕事ってどうしたらできるんだろう…?)
そんな時、ある外国人の訪問介護経営者と出会いました。
彼が自宅で訪問介護事業を運営している様子を見て、

(介護事業って、自宅でもできるんだ…!)
自分で事業を運営すれば、母と弟を守りながら働けるかもしれないと、希望が湧きました。

(この人のやり方を真似すれば、母と弟の日常生活や大切な支援者、自分の生活も守れるかも…!)
これが、私にとって唯一の希望に感じられました。
私の人生計画と実績は、
👉『高校生の私が描いた夢――弟と家族を守るための福祉起業ストーリー』
で詳しく説明しています。
3-2.きょうだいを理解しようとした
弟の行動の意味や望みを観察し、理解する努力を続けました。
障害特性だけでなく、成長を助ける方法も意識して接することが大切です。

(どういう状態か分かれば、振り回されずに済む…)
これは、福祉の支援でも使われる**介護過程(PDCA)**を常に回している状態です。
介護過程については、
👉『障害児家族にもオススメする介護過程とは(前編1)』
👉『障害児家族にもオススメする介護過程(全体像まとめ)』
で詳しく解説しています。
結果として、私の福祉職適性は大きく伸びました。
専門学校で教科書を見たとき、

(思っていたことが全部言語化されている…!)
と驚きました。ほかの生徒は理解するのに必死でしたが、私の理解力は、きょうだい児としての経験から自然と身についた能力に近いものでした。
3-3.身近な経験から福祉を学んだ
私は母や弟を支える中で、福祉制度を詳しく知らなくても、家庭や現場での経験を通して自然と「支援が必要な場面」や「助けになる行動」を学びました。
例えば、弟が施設や通院で困っているとき、本人と家族の負担を最小にするサポートを観察・試行錯誤しました。
この経験は、専門学校で学ぶ内容とリンクし、理解がスムーズになりました。
制度やルールの知識は浅くても、現場感覚や人の気持ちを読む力が育ち、福祉職としての基礎力につながったのです。
発達障害児への具体的な支援については、
👉『こだわりとは、わがままなのか?──椅子へのこだわりから考える支援の正しい視点』
で詳しく解説しています。
3-4.自分の強みを理解した
弟の気持ちを通訳してきた経験や忍耐力など、自分の強みを理解することで、家族の中で自分ができることを見極め、負担を抱え込みすぎず行動できるようになりました。
高校生の時、私は自分の怪力と介護過程(原因分析力や課題抽出力)が他者より秀でていることに気づきました。
暴れる障害児に対しても、冷静に対応できました。

(あの子は暴れているんじゃなくて、伝わらなくてイライラしてるだけだ…)
他の人は逃げていましたが、私は分析力と度胸で対応できました。
この能力を仕事に活かせば、助かる人がいると直感しました。
発達障害児への段階的支援については、
👉『段階的支援の理論背景と実践― しょーくんのケースから学ぶ、科学的に裏付けられた支援の考え方(家族向け)』
👉『急な行動変容はリスク ― 段階的支援の科学的指導』
で詳しく解説しています。
4.私の事例からのまとめ
きょうだい児・者が抱える悩みは、
普通なら考えなくていいことまで考えざるを得ない精神的な負担です。
私は小学生の頃から弟のことを考え始め、
中学生になると親の老後への不安を抱え、
高校生になる頃には自分の人生の歩み方を模索していました。
家庭と仕事の板挟みで、私の選択肢は大きく分けて3つしかありませんでした。

- 家庭を優先して仕事を捨てる
- 仕事を優先して家庭を捨てる
- 自分で事業を立ち上げる
実際に私は、外国人経営者との出会いをきっかけに希望を見出し、
10年の下積み経験を経て、介護事業の立ち上げという道を選びました。

(介護事業って、自宅でもできるんだ!
これなら母と弟を守りながら、自分の人生も歩めるかも…!)
この希望は、あの出会いがあったから生まれました。
あの出会いがなければ、今の私はありません。
伝えたいこと
- 私の経験は、同じ状況で悩む人にとって希望の一例になり得る
- ただし、この道が全ての人に再現可能かというと、そうではない
- 報酬改定による収入変動や制度上の制約など現実的な制約がある
- それでも、希望として示す価値はある
悩んでいる人へ、あーちゃんからのメッセージ
きょうだい児として育つと、悩みや不安は確かに重いものです。
でも、一人で抱え込む必要はありません。
福祉の制度も少しずつ整いつつありますし、自分の人生は自分で歩んで大丈夫です。
現実を見ながら歩んできた私からのアドバイスは、こうです。

自分の強みを理解し、
目標を立てて行動を振り返り、
改善しながら進めばいい。
希望を持つだけでなく、
行動を積み重ねることで人生は変えられます。
自分の強みを少しずつ理解して、できることから行動してみてください。
そして、行動の結果を振り返り、改善していく
――つまり、PDCAのように少しずつ前に進むことが大切です。
希望を持つだけでなく、少しずつ行動を積み重ねることで、未来は変えられます。
私はそうやって生きてきました。
こうした道を選ぶ人は多くないと思います。
正直、低賃金だからおすすめはできません。
それでも私は、親と弟を守りながら、自分の生活も安定させることができて、ある種の満足感を得られています。
