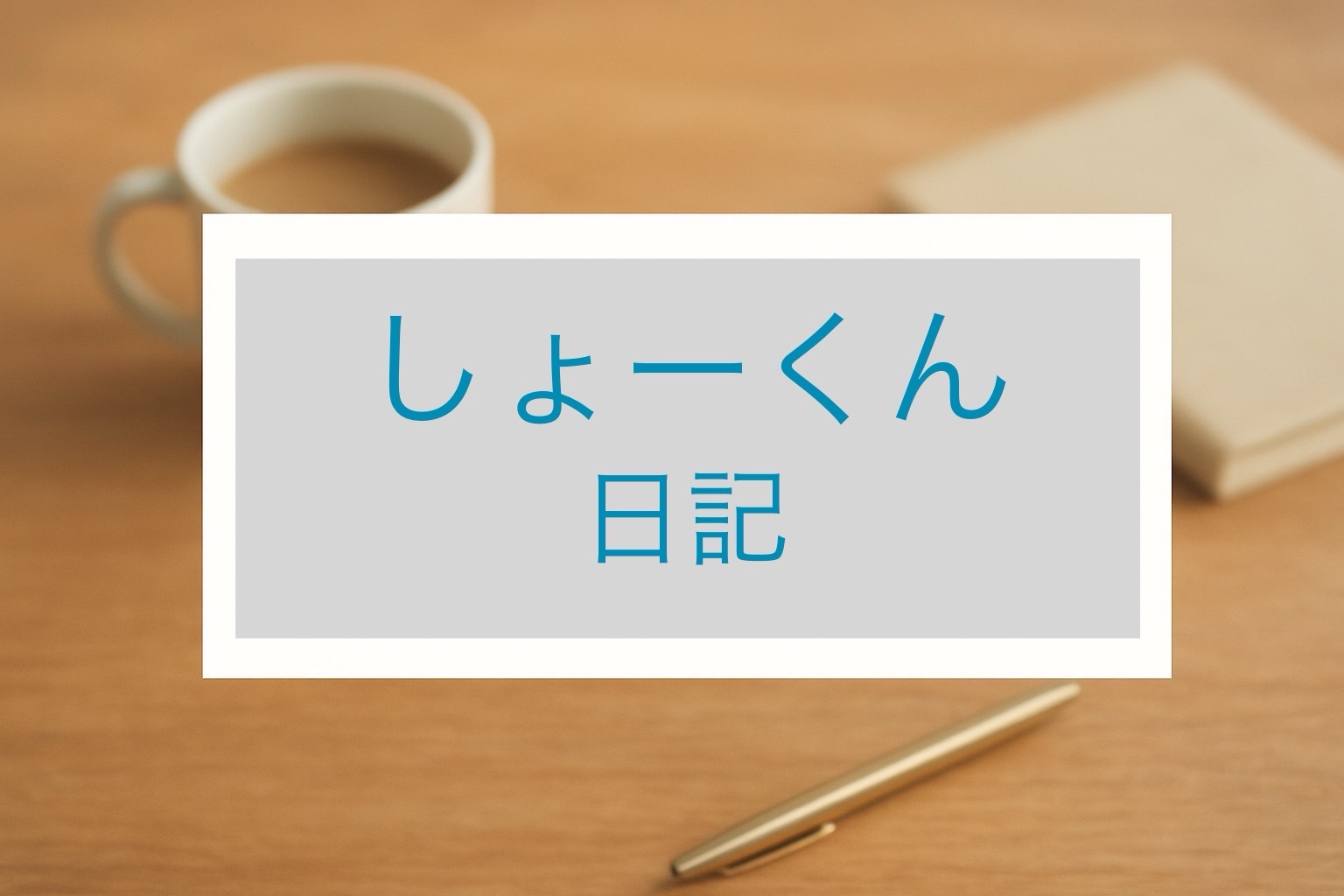名前が変わっただけで、子どもや家族の困難は本当に減ったのでしょうか?
言葉は変わる。でも、本質は変わらない
日本では法律や制度の上では今も『発達障害』という言葉が使われています。
ただし、学術や医療の世界では、『神経発達症』という表現が使われることも増えています。
つまり現状は“学術的には神経発達症、社会的には発達障害”という二重構造になっているのです。
しかし、正直なところ、言葉だけ変わっても困っている本人や家族の生活が大きく変わるわけではありません。
表現の変更だけで「配慮していますよ」という空気が漂う社会には、どうしてもイラッとさせられます。
実際に子どもや利用者に関わる支援は、「発達障害」と呼ばれていた頃とほとんど変わらないことが多いのです。
言葉の変化だけで、本人の困難や支援内容が改善されるわけではない。
それどころか、言葉の変更によって現場で混乱が生じることもありえます。
名前より大事なのは「支援の中身」
障害者の「障害」という言葉は、「特性によって生活や学習に障害(支障)が生じている状態」を指します。
従来はICIDH(国際障害分類)に基づいた考え方が主流でしたが、現在はICF(国際生活機能分類)を用いるのが主流です。
障害を考えるときは、本人の特性だけでなく、環境や支援が、生活のしやすさを大きく左右することが重要です。これはノーマライゼーションの理念にも通じます。
※ノーマライゼーションとは、障害の有無に関わらず、誰もが地域や社会で普通に生活できることを目指す考え方である。
環境や周囲の理解、支援の有無によって生活のしやすさは大きく変わります。
言葉の変更は無意識の偏見や差別を避けるためには必要ですが、本質を理解せずにラベルだけを変えて満足している人たちがいるのが、現場のフラストレーションの原因です。
例えば、ある子どもは落ち着きがなく、授業中に席を立ってしまうことがあります。
これを「神経発達症」と表現を変えたものの、具体的な支援方法は以前と変わらないなら、支援を受ける側的には依然として名前を変えた意味はない。
表現が変わっただけでは、困難は解消されないのです。
医療現場の現実
医療現場を見てみると、さらに複雑です。
神経発達症の多くは生まれつきの脳の特性によるもので、「治す」ことは難しい。
そのため、医師の中には「医学的に治せないもの=重要ではない」と考える人もいます。
実際、家族に対して「治せません」と突き放すような態度をとる医者も存在します。
無意識かもしれませんが、本人や家族にとっては大きな傷になります。
※これは著者の現場経験に基づく記述です。
私自身、訪問介護や福祉現場で家族から相談を受けることがあります。
「診断はついたけど、医者には治せないと言われた。じゃあどうすればいいの?」という声です。
言葉や診断名を変えても、現実には生活支援や環境調整が不可欠です。
それなのに、医療の現場で「治せないから仕方ない」と突き放されると、本人も家族も途方に暮れてしまいます。
医学の世界で診断名や表現が変わっても、実際に支援を提供するのは福祉や教育の現場です。
医師が「治せない」と突き放す一方で、生活や学習の困難を軽減する取り組みは、現場や家族の手に委ねられています。
医学の名称変更は当事者や家族にとってはほとんど意味がなく、支援の本質とは切り離されているのです。
制度や社会のギャップ
学校や職場、行政の支援制度も同じです。
診断名が「発達障害」でも「神経発達症」でも、特性に合わせた支援は変わりません。
しかし、制度や書類上の表現に合わせることばかり優先されれば、現場の柔軟な調整や本人に寄り添った支援が後回しになることがあります。
現場で行う支援は個別対応の工夫が必要です。
ある利用者は、感覚過敏が強く、特定の音や光に過敏に反応します。
これに対し「神経発達症」とだけ記載されても何もわかりません。
支援の現場では本人の感覚特性に合わせた環境調整が必要です。
書類上の言葉だけでは、この現実は伝わらない。
一般の人も追いついていません。
ラベルを覚えるだけで「理解している」と思い込んでいるケースが多く、現場にいる側としては「本質をみてほしい」と言いたくなるのです。
言葉より大事なもの
結局、重要なのはラベルではありません。
言葉の変更は無意識の偏見や差別を避けるためには必要です。
しかし、名前が何であろうと、最終的に本人の生活をどう改善できるかこそが大事であり、言葉は社会的配慮や医学的分類の手段に過ぎない。
医療、行政、学校、職場—どこであっても、表現だけ整えるのではなく、実際に困難を減らす取り組みが求められています。
例えば、職場での就労支援の場合、ADHDの特性を持つ社員に対して、机の配置や作業の順序を工夫するだけで集中力が格段に上がることがあります。
診断名や表現を変えるよりも、こうした具体的な支援こそが本人の生活の質を変えるのです。
言葉の背後にある本質を忘れない
医学的に言葉が変わっても、困難は変わらない。
表現だけで満足して本質を見ない態度には、強い違和感があります。
言葉は社会的配慮の手段に過ぎない。
私たちは常に「特性に寄り添うこと」「困難を理解し支援すること」を忘れずに、言葉の背後にある本質に目を向け続ける必要があります。
特性や困難に寄り添った理解と環境調整こそが、本人の生活の質を変えます。
言葉の変更は無意識の偏見や差別を避けるためには必要ですが、それは社会の理解が足りていないという裏返しでもあります。
実際の支援と医学の考え方の違い、そして社会の福祉への理解不足――この3つのズレがよく見えてきます。