目次
1. ケースの状況
施設での交流イベントで、弟は特定の椅子にどうしても座りたがりました。
職員は別の席に誘導しようとしましたが、弟は譲らず、椅子の取り合いになりかけました。
一見「わがまま」に見える行動ですが、実際には行動の目的が異なることが明らかになりました。
ここで重要なのは、職員が「誘導する行為」そのものに固執せず、
弟(利用者)が落ち着き、安心することを目的として捉えることです。
この柔軟性の有無が支援の成否に大きく影響します。
私はまず制止せず観察し、手の動きや表情、視線を注意深く見て、
単に座りたいだけではなく、椅子そのものにこだわりがあるのではないかと推測しました。
2. 支援の実践(具体例)
① 状況の観察
- 職員や周囲の対応を制止せずに観察
- 弟(利用者)の表情や手の動き、椅子へのこだわり方を注視
- 「譲れない理由が椅子そのものか、場所か」を推測
- 観察を通じて、行動が単なる自己主張ではなく、安心感を確保するための行動である可能性を探ります
② 本人への確認
- 弟(利用者)に直接質問:「この椅子に座りたいの?」「他の席でも大丈夫?」
- 言葉だけでなく、指さしや表情など非言語的反応も確認
- 結果、椅子そのものへのこだわりが明らかに
- ABAのABC分析でいう「行動の目的(Behavior)の特定」に相当
- この段階で、行動の背景を正しく理解することが、今後の支援計画に直結します
③ 環境調整
- 職員に事情を説明:「お客さん席ではなく、この椅子がよいとのことですが、入れ替えは可能でしょうか」
- 職員が了承し、椅子を入れ替え
- ポイント:誘導の「手段」ではなく、行動の「目的」を満たす柔軟な対応を優先
- 小さな配慮が本人の安心感を大きく支え、トラブル防止にもつながります
④ 安心して参加できる工夫
- 弟(利用者)が椅子を移動する際は安全に配慮
- 周囲の利用者や職員に簡単に説明してトラブル回避
- 移動後、落ち着いてイベントに参加
⑤ 振り返りと評価
- 行動の目的が満たされ、安心して参加できたことを確認
- 同様の状況への対応フローを記録
- 家族・職員間で「椅子へのこだわり=安心感のサイン」と共通認識を共有
- これにより、次回以降もスムーズで安全な支援が可能になります
3. 理論的背景(具体例付き)
ABC分析(行動の機能理解)
- Antecedent(先行条件):交流イベントでの椅子の配置や周囲の状況
- Behavior(行動):特定の椅子に座ろうと譲らない
- Consequence(結果):家族・職員が確認・環境調整 → 弟(利用者)が安心して落ち着く
分析により、行動の目的は「お客さん席に座りたい」ではなく、特定の椅子で安心したいことが明確になりました。制止だけでは目的が満たされず、行動が固定化する可能性があります。
氷山モデル(心理的背景)
- 表面的行動:椅子にこだわって譲らない
- 心理的背景:安心感や納得感の確保、環境へのコントロール感の保持、突発的不安回避
氷山モデルを用いることで、見える行動だけでなく、見えない心理的要素まで考慮した支援が可能になります
機能的評価(Functional Assessment)
- 行動の目的や機能を明確化
- 弟に直接確認することで行動の目的を特定
- 環境調整(椅子の入れ替え)で行動が安定
職員へのメッセージ:誘導するときは、表面的な行動や物体に固執せず、行動の目的を満たす柔軟な手段を選ぶことが重要です。
4. 介護過程として整理
- 観察:行動を制止せず注視
- アセスメント:行動の目的や背景を推測
- 支援計画:環境調整や確認方法を検討
- 実施:本人と職員の両方に対応を共有
- 評価:行動安定とイベント参加を確認
介護過程を意識することで、支援の再現性と安全性が高まります。
5. わがまま=教育不足の誤解
一般的に誤解されやすいことですが、「わがままを許さず我慢させることが教育になる」と考える人もいます。しかし、専門家の視点ではこれは誤りです。
- 行動の目的を無視した制止では学習にならない
- 不安やストレスが学習を阻害する
- 信頼関係を損ない、自己表現や社会参加意欲を阻害する
- 表面的に制止するだけでは行動問題が悪化するリスクがある
指導者への提言:柔軟に手段を変え、行動の目的を満たす支援が、学習や成長のチャンスを生みます。
6. まとめ
- 表面的行動だけで「わがまま」と判断せず、背景や目的を理解する
- 安心感・納得感を満たすことで行動は安定し、学びや社会参加の機会も広がる
- 信頼関係を築くことが、教育や支援の土台になる
- ABA/FBA、氷山モデルなど行動科学の理論を応用すれば、家庭でも施設でも安全で学習効果の高い支援が可能
💡 ポイント
・「我慢させる教育」は逆効果
・支援は「行動の背景理解+環境調整+本人確認+柔軟な誘導」が必須
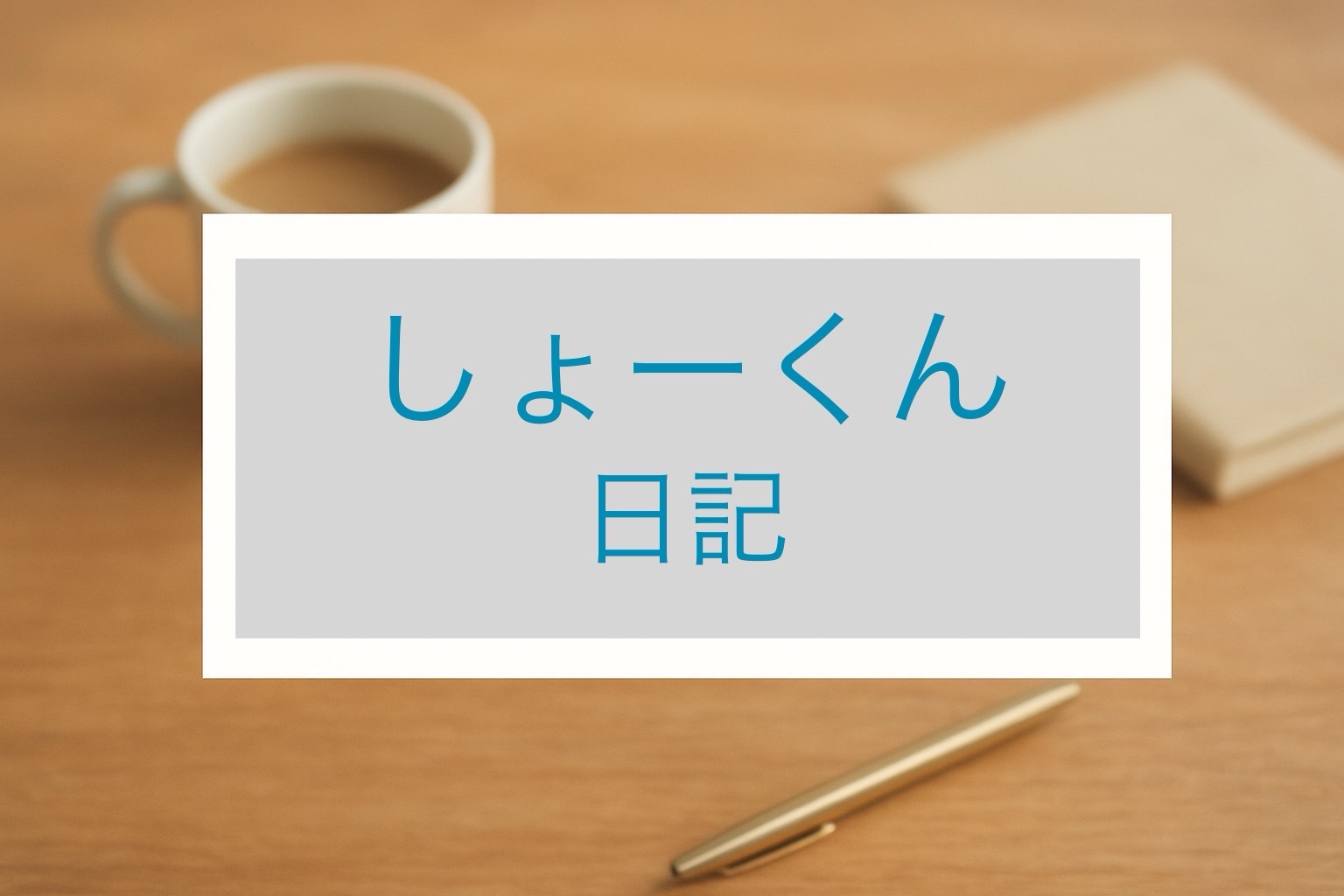

コメント