第四章 制度改善のための具体的な提案
~訪問介護制度を持続可能にするには~
現状として、「支援があっても暮らせない」「人手が足りず希望の時間に入れない」といった事態が、当事者・家族・ヘルパーすべてを追い詰めています。
これは単なる人材不足ではなく、「制度設計が現実と乖離している」ことに起因する構造的問題です。
家族介護の限界と、“家庭による支援を前提とした制度思想”が、介護の持続可能性を揺るがしているのです。
訪問介護制度を持続可能にするために、以下の制度設計の見直しを提案します。
① 求めるのは「公平な評価と分類」
インフレが続く中、訪問介護の単位だけ下げられています。
現状のままでは訪問介護職員の給料が上げられません。
基本報酬の見直し
現在の訪問介護では、1件ごとのサービスに対して支払われる「基本報酬」が非常に低く設定されています。
この基本報酬(単位)から、事業所の運営費(事務員等の人件費、使い捨て手袋等の備品、移動費など)と、介護職員の給与がまかなわれます。
処遇改善加算も大事ですが、基本報酬の元になる単位を見直してください。
施設的訪問型(効率運営が可能なケース)
- 同一建物での対応
- 移動時間・調整が最小限
- より低単価でも運営が成り立つ
在宅型訪問介護(個別支援型)
- 1人ひとりの家を回る
- 移動時間・調整労力が大きい
- 報酬水準を上げないと成り立たない
このように運営形態に大きな違いがあるにもかかわらず、報酬体系が一律である現状では、在宅型訪問介護が一方的に不利になる設計です。
本来は、それぞれの特性に応じた報酬が設定されてこそ、公平な制度といえるはずです。
ではどうすべきか
運営形態ごとに報酬を分ける
- 類型ごとに報酬設定を変える
→ 同一単価にせず、在宅型には高単価設定が必要 - 施設的運営型も正当に評価する
→ 経営努力を否定せず、むしろ「モデル事業」として区別・活用する - 透明な仕組みと運営要件を設ける
→ たとえば「同一建物〇名以上の対応は施設型扱い」など明確な基準を示す
そのうえ、従来型の訪問介護は、収益のほとんどが人件費に消えます。残ったわずかな収益で備品を買っている状態。最低賃金が上がっても、たとえ利用者が増えても、1人のヘルパーが1日に訪問できる件数には限界があります。事業者の収益が伸びなければ、今以上に働く環境を整えたり、給料を上げていく事は困難です。
ケア記録や移動時間も報酬算定に含める
今回訪問介護の報酬単価が下がりましたが、そもそも訪問介護という仕事は、利用者との接触時間だけでなく、移動や記録といった「見えないケア業務」にも対価が必要です。
【以下のような背景があります】
- 訪問と訪問の間に移動時間が発生する
(これに介護報酬は出ないが、給料は発生する。給料に反映していない事業所もある。) - 利用者によっては短時間・軽度のサービスしか必要としない(=単価がさらに低い)
- 1人のヘルパーが1日に多くても4~5件程度しか回れない(地理的制約もあり)
このように、基本報酬が低いままでは、事業所の収益が限られ、十分な人員配置や待遇改善ができない構造になっています。
【結果として】
- ヘルパーの確保が困難になる
- 利用希望者がいても、受け入れられない
- 時間帯や内容によっては、サービス提供そのものが不可能になる
つまり、訪問件数が増えても、採算が取れず、現場が疲弊してしまう悪循環が生まれているのです。
②「訪問介護=社会インフラ」という位置付けの再定義
訪問介護のメリットは大きく分けると2点
- 利用者のQOL(生活の質)が、高く保ちやすい。
- 現実には、そもそも入所できない人もいる。
くわしくはこちら
制度内での位置づけを、「家庭の補助」ではなく「地域生活の根幹を支えるインフラ」に見直すべき時期です。
構造を変えるためには、基本報酬そのものを見直し、訪問1件あたりの単価を引き上げる必要があります。
それによって、以下のような改善が見込まれます。
- ヘルパーに適正な賃金を支払えるようになる
- 採用・定着が進み、人手不足が緩和される
- 利用者に対し、安定して希望のサービスを届けられる
※訪問介護は、人との接触時間や信頼関係の蓄積が何よりも大切なサービスです。
「数をこなす」効率重視のモデルには適していないからこそ、1件1件に対する評価(=報酬)が見合ったものにされるべきです。
③ ヘルパーへの特別控除制度の創設
もっと働ける介護職もいる。しかし…
社会に貢献しても、介護職はいつまでたっても報われない──
低報酬・低評価・少ない手取り。
人の尊厳を支える、専門性の高い仕事であるにもかかわらず、世間の理解はまだまだ乏しいのが現実です。
給料が上がっても、手取りがほとんど変わらない。
評価も名誉も得られず、達成感さえ薄れていくなかで、介護職が「使い捨ての駒」のように扱われる現場に身を置いてきました。
それでも、私たちは誰よりも「老後」や「障害」、そして「社会の限界」と向き合ってきました。
老いは必ず訪れます。
障害も、誰にとっても他人事ではありません。
それなのに、日本社会にはまだ“当事者意識”が根付ききれていないように感じます。
介護は長らく「家族が担うもの」とされてきました。
この歴史の延長線上で、いくら専門性を磨いても、介護職が正当に評価されることは難しいのかもしれません。
私は今の日本のあり方を見て、そう思わずにはいられません。
人の価値観や社会意識は、そう簡単には変わりません。
でも、せめて介護職員が“公務員”のような安定した立場で働けていたなら、ここまで軽視されることはなかったのではないか──そう考えることがあります。
実際、スウェーデンやドイツなどの国では、介護職は十分な賃金水準が確保され、社会的にも高く評価されています。
だからこそ、日本でも「介護に真剣に向き合ってきた人が受けられる税控除や将来保障」といった、具体的な支援制度があってもよいのではないでしょうか。
おわりに
「家庭で支える」という方針のもとに成り立っている訪問介護制度。
現場で訪問介護を提供する私たちは、制度がその「前提」に甘えすぎているのではないかと感じています。
訪問介護は、利用者の生活の基盤であり、地域コミュニティの重要な支えです。
しかし、現在の制度は「家庭が支える」という前提に立ち、現場の実態を十分に反映していません。
報酬の低さや制度の複雑さは、現場の担い手を疲弊させ、サービスの質や量の低下を招いています。
このまま制度を放置すれば、訪問介護は持続不可能となり、利用者や家族、そして働く介護職員すべてが不利益を被ります。
私たちは、訪問介護の担い手が正当に評価され、安心して働ける環境の実現を心から願っています。
介護の現場は、誰かの“善意”や“無償の愛”によってかろうじて成り立っているのが実情です。
この構造を放置すれば、担い手がいなくなり、制度そのものが空洞化してしまいます。
だからこそ、現場の声を聞いてください。
そして「人が働ける仕組み」を、制度の中に組み込んでください。
現場の声を行政や政策決定者が真摯に受け止め、構造的な改革を進めることが、地域の生活を守るための唯一の道です。
地域を支えるインフラとしての訪問介護を再評価してください。
この制度設計が変わらなければ、将来私たち自身や家族が『介護を受ける側』になったとき、支援を受けられないリスクすらあるのです。
🔽 コメント・ご意見をお寄せください
ご覧いただきありがとうございました。
制度設計に関心を持っていただけた方、どうか現場の声を拾い上げてください。
次回
B型作業所の未来に、不安と願いを込めて【前編】
──弟の働く場所が、制度の中で削られていくかもしれない
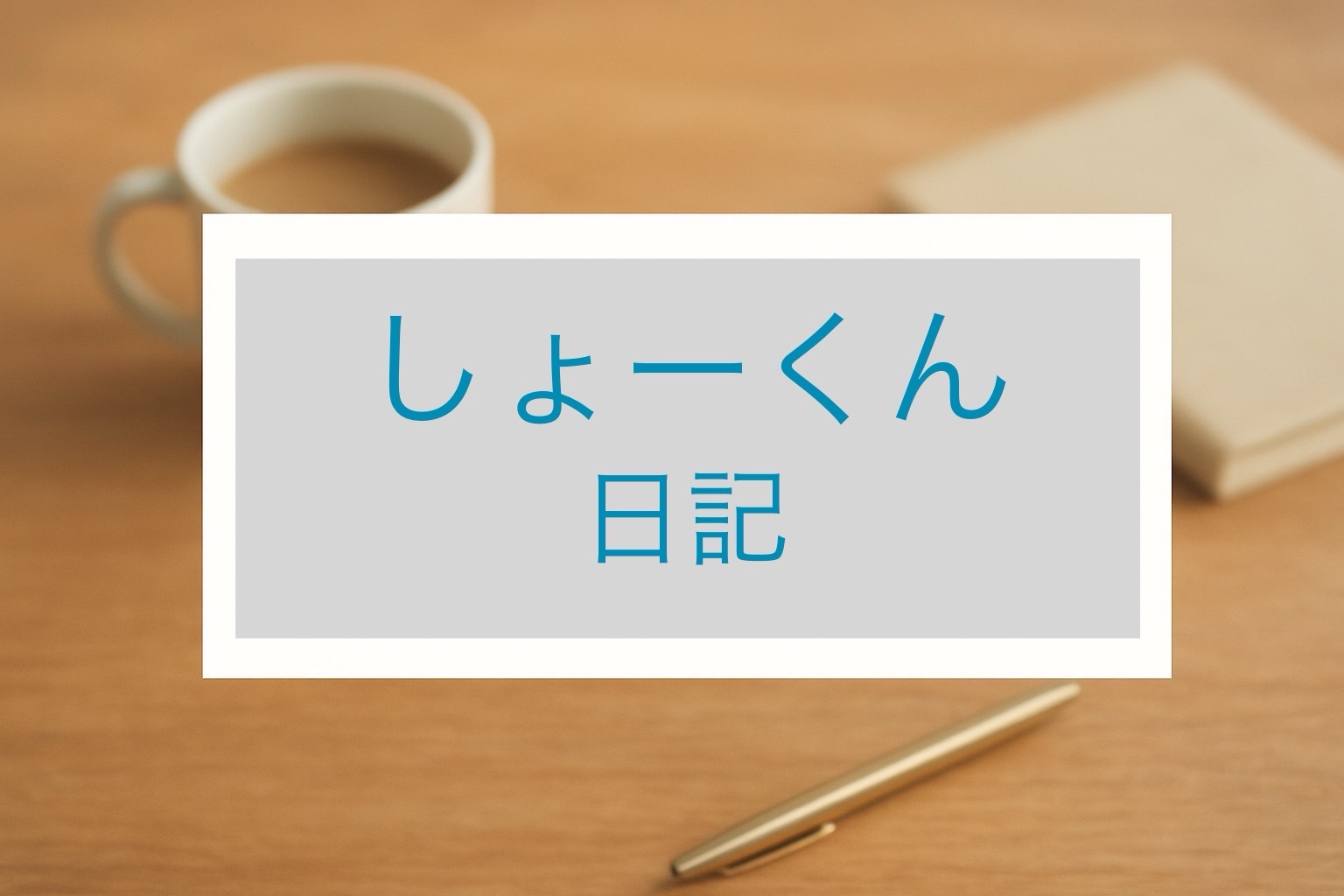

コメント