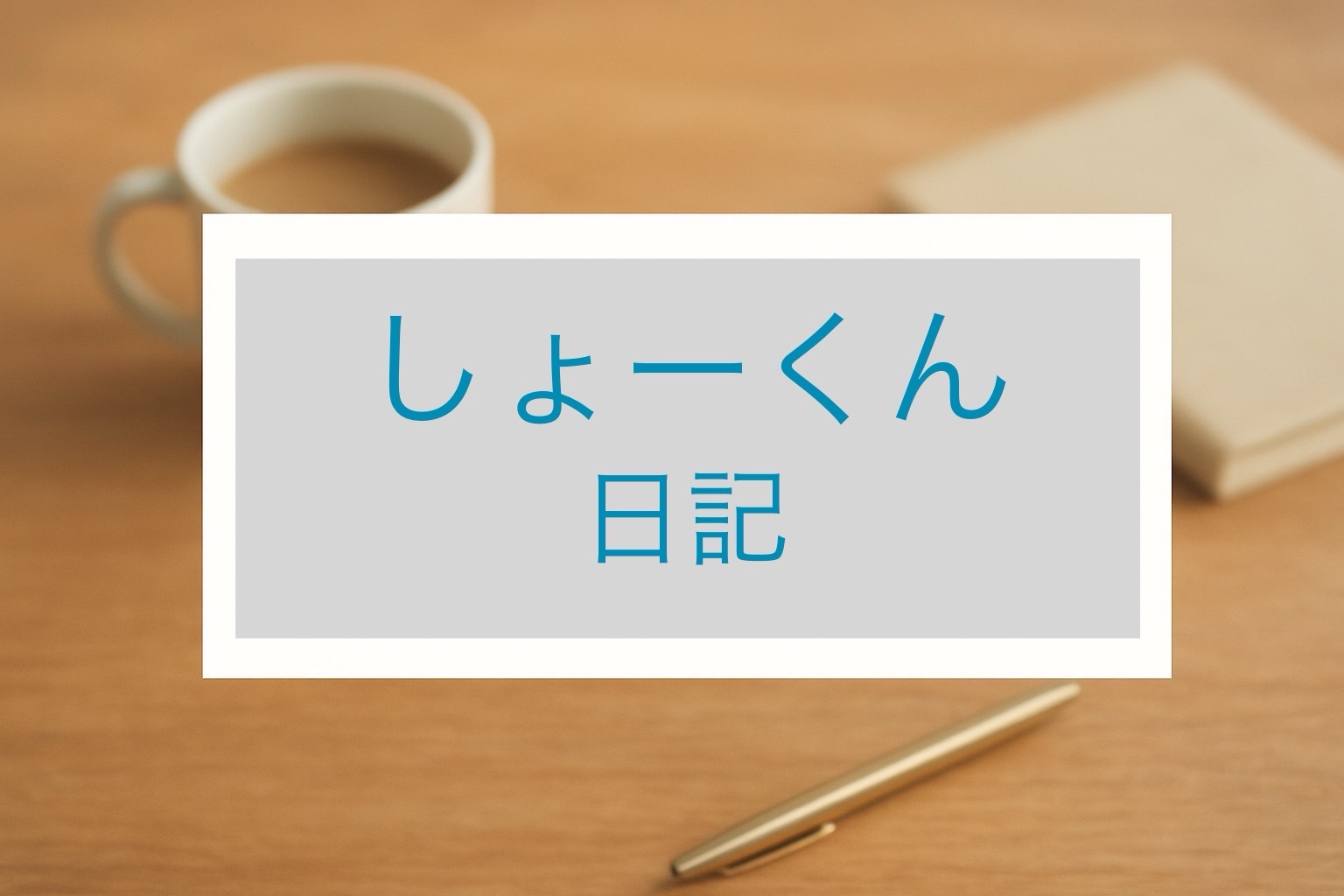支援の現場でよく耳にする「段階的支援」は、単なる手順ではなく、科学的・実証的に効果が確認された方法に基づいています。
特に発達障害や行動に困難を抱える方への支援では、本人が安心して行動できることはもちろん、支援者や周囲の人の安全も確保することが重要です。
今回は、しょーくんのケースを例に、段階的支援の理論と実践を解説します。
事例の整理
- 姉は足を怪我しており、スリッパを履くと転倒リスクが上がる
- しょーくんは姉にスリッパを履いてほしいという意向を持つ
- しょーくんはスリッパを姉の足元に持ってくる行動をとる
その結果、姉の転倒リスクがさらに高まっている
この状況を安全かつ学習効果のある支援に変えるため、科学的な行動分析の理論を活用しながら、説明します。
1. ABA理論とシェイピングの正確な適用
ABA(応用行動分析)は、行動が環境との関わりで学習されることに基づき、科学的に検証された方法で望ましい行動を増やす手法です。
シェイピング(段階的学習)の原則を正確に適用する場合は、目標行動を明確に定義し、逐次的に近づく行動を小さなステップで強化します。 今回のケースでは、目標は「しょーくんが自発的に安全な代替行動を選択すること」です。 ABAの手順として、各ステップの定義と強化基準を事前に設定し、科学的に記録を取りながら支援することが推奨されます。
2. ABC分析で行動の原因を明確化
ABC分析は、行動の機能を理解する科学的手法です。
- A(Antecedent)先行条件:スリッパが目の前にある/姉が座っている
- B(Behavior)行動:スリッパを姉の足元に持ってくる
- C(Consequence)結果:姉の転倒リスクが上がる/支援者が反応する
この分析により、行動が本人の意図(姉に履かせたい)によって現れていることと、安全上の問題が生じていることを明確に区別できます。
3. タスク分析の科学的手順
タスク分析は、複雑な行動を小さなステップに分解し、各ステップの習得を科学的に確認しながら指導する方法です。
例(安全配慮を組み込んだ手順)
- スリッパを手に取る
- 姉の足元に直接運ばず、安全な位置に置く
- 代替行動(棚に戻す、決められた場所に置く)を自発的に選ぶ
各ステップを小さく区切り、行動の記録と強化のタイミングを明確化することで、安全かつ科学的に支援できます。
4. 代替行動の差別強化(DRA)の正確な適用
DRAは、問題行動を減らすために機能的代替行動を科学的に強化する手法です。
しょーくんの場合
- スリッパを直接姉に持っていかず、安全な場所に置く行動を強化
- 棚や指定の場所に戻す行動を強化
重要ポイント:強化の対象は「行動そのもの」ではなく、「自発的に安全な代替行動を選んだこと」です。ABAの科学的手順に沿って、頻度やタイミングを記録しながら行うことで、学習効果が最大化します。
5. PBS(ポジティブ行動支援)の科学的適用
PBSはABAの理論を日常生活に応用したもので、科学的根拠に基づき行動支援を設計します。
- 本人の尊厳を守る
- 問題行動の機能を評価する(FBA:Functional Behavior Assessment)
- 環境を整え、安全で望ましい行動を促す
しょーくんの場合、FBAに基づき「スリッパを持っていく行動」の機能を理解し、環境調整(安全な置き場所の設置)と代替行動の強化を組み合わせます。これにより、本人も支援者も安全で安心できる行動環境が実現します。
6. 安全で科学的な段階的支援のまとめ
今回の事例から分かることは、科学的根拠に基づいた段階的支援を正確に適用することで、本人の意向を尊重しつつ安全確保が可能になるという点です。
ポイントは以下の3つです
- 行動の背景を明確にする ABC分析やFBAで行動の目的やリスクを科学的に把握する。
- 段階的に学習させる シェイピングやタスク分析で、小さなステップに分けて安全な代替行動を習得させる。
- 安全な行動を正しく強化する DRAやPBSを活用し、自発的な安全行動を強化することで、学習効果と安全の両立を実現する。
この視点を現場で意識するだけでも、本人・周囲双方にとって安全で効果的な支援につながります。